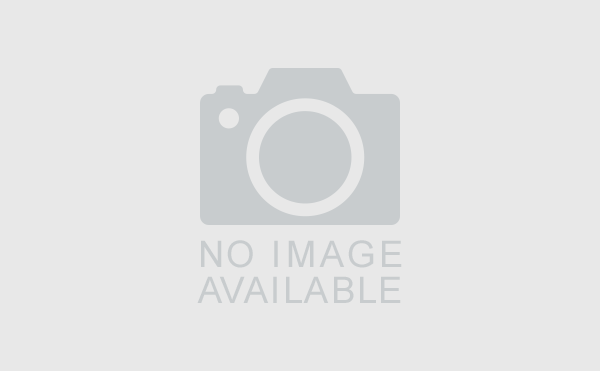聖書講話「日常生活の中に聖所を ー祈りの宗教生活(後編)ー」使徒行伝2章41~47節
イエス・キリスト亡き後、弟子たちに聖霊降臨(ペンテコステ)が起こったのは、ある婦人の家であったといわれます。その後、彼らは生活の中で信仰を共にしました。日常の中に信仰が息づき、食事をするにも仕事をするにも、また寝床に就く時も、神様への感謝と祈りが伴う。それが原始の福音の姿です。前回に続いて、聖霊を受けた後にどのようなことが大事かを、使徒行伝2章から学びます。(編集部)
使徒行伝2章に、120人のイエス・キリストの弟子たちに聖霊が降(くだ)ったペンテコステの日の出来事が記されています。その日、1日に3000人の者が使徒ペテロの言葉に悔い改めて、イエスを救い主キリストと信じました。
そこで、彼の勧めの言葉を受けいれた者たちは、バプテスマを受けたが、その日、仲間に加わったものが3000人ほどあった。
使徒行伝2章41節
ここで、1日に3000人がバプテスマ(注1)を施された、とある。どうやって施したのだろうかという問題があります。当時のバプテスマというのは水の中に全身を浸すような洗礼でしたから、そうすると、果たして3000人分の水があっただろうか、どのように施したのかということが、今のキリスト教会の人たちには疑問になる。
教会では、一人ひとりを説得して入信を勧める。大概、教会に10回出かけて洗礼を受けるのは早いほうだというから、それでも2カ月はかかる。ペテロが話して、「あなたは、三位一体の教理を信じますか」などと試問しておったら果たして時間が足りるかしら、といってキリスト教の既成概念で読みますから、どうしてもわからない。
しかし、それは実に愚(ぐ)な話です。3000人の者たちが水の洗礼の儀式をするとなったら、いちいち着替えたり、祝禱(しゅくとう)したりして、どれだけ時間がかかるか。とてもありえない。だからこの記事は誇張だ、と彼らは言います。
けれども私は、そうは思いません。3000人といっても、皆ユダヤ教徒ですから、異邦人が改宗する場合のように、当時のユダヤ教の掟(おきて)に従った、いわゆる水の洗礼はほとんどが必要でなかった。ですからこれは、”聖霊にバプテスマ”されたことを言っているんです。
「ヨハネは水で洗礼(バプテスマ)を施したが、おまえたちは日ならずして聖霊にバプテスマされるであろう」と、イエス・キリストが使徒行伝1章5節でおっしゃっています。
こうやって、まず120人の者に聖霊が臨みましたら、500人のうちの取り残されておった380人の者たちも、次々と祝福された。また、その他の人たちも皆、電気にビリビリ感電するように聖霊にバプテスマされた。1日に3000人がコンバージョン(回心)したというのであります。
このように、神の霊が働きます時に、多くの人々が続々と信仰に入ってくるものです。

(注1)バプテスマ
一般には、キリスト教の洗礼のこと。元は、ギリシア語で「浸すこと」の意。当時のユダヤ教で、体を清める時や、異教から改宗する時に行なった儀式に由来する。
神の霊が働く伝道
北九州の幕屋では、長く銀行などに勤めておられた平岡基邦さんが赴任してからというもの、ほんとうに幕屋のようすが変わって集会が息吹き返し、次から次に人が集まってくる。集会室に入り切れない、というお話を聞いて驚きました。この平岡さんにせよ、ほかのだれ君にせよ、世の中で働きながら、東京のこの集会で一緒に学んだ人たちです。そういう人たちが、立派に伝道をやっておいでになる。
ここに、いわゆる聖職などと称する牧師階級、神父階級というものはないのです。ペンテコステは、私たちにそれを認めません。人間に変わりはありません。最初から牧師になって生まれてくるわけでもない。大事な、尊いことは、新しく造り変えられること、神の御霊が注がれることです。天使たちのもつ不思議な生命が、私たちに注がれることです。
その時にこうやって平岡さんのように、立派な伝道を繰り広げてしまう。堅い仕事を長くされてきた方なので、どうかしらと皆が心配しました。だが、伝道は人間がするのではない。キリストの手先となって、神の霊が働いてなされる伝道が始まらない限り、決して勝利することはありません。彼もやるんですから、私たちもしようではありませんか。
1日に3000人の者が仲間に加わった。かくして初代教会の基礎が据えられました。
明治時代の初頭、W・S・クラーク大佐を通して、札幌バンドというキリスト者の若者たちの一群が起こりました。大島正健ら十数名の者たちが信仰に入り、その後、内村鑑三や新渡戸稲造たちも加わりました。
また同じころ、L・L・ジェーンズ大尉が熊本洋学校で3~4年、教鞭(きょうべん)を執りながら伝道したら、35名の青年がキリストを信じる盟約をしました。キリシタン禁制が解かれて間もない時のことです。また、その少し前に横浜において、宣教師ヘボンらの祈祷会が信仰復興(リバイバル)状況になった。
こうやって横浜、熊本、札幌と3カ所にリバイバルが起きて、日本に近代キリスト教の基礎が据えられたといいますが、最初、ペンテコステの日に何が起きたかというと、3000人の人をひき付けるような、驚くべき宗教エネルギーが働いたということです。
神の生命が、霊が働かなかったならば、どうして私たちの幕屋が成立したでしょうか。人間の思想や説得力では、とてもできるものではありません。3000人がバプテスマを授かったというのはうそだと、聖書学者のK先生は雑誌に書いておられた。だが、それはほんとうに聖霊にバプテスマされる、一つの霊が注がれるということを知らないからです。
それを、私たちのような、無学で社会的な地位もない者たちが知っている。私たちが置かれた場を、ほんとうに尊びとうございます。そして日々に、もう毎日のように、福音を求める人々が加えられてゆかねばなりません。
初代教会の宗教生活
そして一同はひたすら、使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンをさき、祈りをしていた。
使徒行伝2章42節
ここで、「一同はひたすら(~する)」と訳されている箇所は、ギリシア語の原文では、「(彼らは)じっと持続する、専念する」という語です。彼らは何を持続していたのかというと、使徒たちの「教え διδαχη ディダケー」をです。これは神学のことではありません。信仰の基礎的な話、こうあるべきだという、先輩としての注意のことです。それを固くもちつづけた、固執した、という意味です。
リバイバルが起きましても、一時の感激では信仰が消える。そうではなくて、ひたすら使徒たちの教えを守りつづけることが大事です。さもないと信仰は成長しません。
そして、「ひたすら守る、ひたすら持続する」という言葉は、4つのことにかかります。使徒の教え、信徒の交わり、パンを割くこと、祈り――この4つをもちつづけていた。これは、初代教会の簡単なスケッチを、私たちに見せてくれる言葉です。
まず、先輩たちの教えをどこまでも守りつづけなければ、信仰は伸びてゆきません。
しかし、聖霊にバプテスマされると、何を痛切に感ずるかというと、信仰の友同士の交わりに飢えてきますね。無教会主義だからといって、独りぼっちで信仰するというのではたまらない。だれか同信の友と会うだけでうれしい。これが、「交わり κοινωνια コイノーニア」であります。「互いに分かち与える」という意味です。お互いの心の交流、愛の交流をいうのです。
そして、パンを割き、祈りをすることを固く保っていた、とある。パンを割く、食事をするというのは、日に3度することですから、それが宗教的な意味をもつのか、と人は思うでしょう。しかし、神殿や会堂に参ることが宗教だと思われるときに、初代教会の人々は各家庭に集まって食事をして、祈ったというのであります。
ペンテコステはどこで起きたか。マルコ福音書を書いたマルコの母マリヤという未亡人の家で起きたんです。すなわち、お宮や教会堂でペンテコステの御霊が臨んだのではなく、普通の家庭の広間で臨んだ、ということです。
ここに原始福音とは、宗教がお宮に縛られ、どこかの聖地や聖所に縛られている、という考え方から解放することを意味するのであります。宗教が日常生活に取り入れられて、パンを食べることすらありがたく頂くような生活、これが原始福音の生活である。
ペンテコステの霊が臨む時に、パンを食べても、それが貧しいパンだとしても「うれしいなあ、ありがたいなあ、もったいないなあ」と言って食べることが始まります。ですから、ほんとうに日常生活が宗教でなければなりません。三度三度のパンを食べることの中にすら、宗教的な意味があるのです。日常生活で、パンを割くことでも、どこかに出かけて遊ぶことでも、レクリエーションをすることでも、事業の上においても、宗教的な在り方というものがあるのです。そんな、日常の中に神の霊が伴うような宗教生活、これが大事です。ただ日曜日、教会堂に礼拝しにゆく時だけが宗教生活であるなら、それはうそです。
毎日、外を歩く時でも、歩きながら口に賛美がついて出るのが、本当の宗教生活というものです。日常生活に宗教がやって来る。これは、ペンテコステの霊が私たちに臨む時に、ほんとうにそうなるんです。何をしてもうれしい。何を頂いてもありがたい。
ペンテコステといっても、一時の感激に終わりやすいように思うかもしれない。それに対して、「使徒の教えに、交わりに、パンを割くことに、祈りをすることに、ずっと専念していた」と書いてありますから、初代教会の人々の心にそのような宗教生活が根ざしました。また、ペテロたちがそのように指導しました。どうか、私たちは絶えず、この祈って祈り抜くような信仰生活を送りたいと思います。
家庭こそ聖所
みんなの者におそれの念が生じ、多くの奇跡としるしとが、使徒たちによって、次々に行われた。信者たちはみな一緒にいて、いっさいの物を共有にし、資産や持ち物を売っては、必要に応じてみんなの者に分け与えた。そして日々心を一つにして、絶えず宮もうでをなし、家ではパンをさき、よろこびと、まごころとをもって、食事を共にし、神をさんびし、すべての人に好意を持たれていた。そして主は、救われる者を日々仲間に加えて下さったのである。
使徒行伝2章43~47節
「みんなの者におそれの念が生じ、多くの奇跡としるしとが、使徒たちによって、次々に行われた」とありますが、聖霊に満たされる時に、神が臨在したもうことのありがたさ、厳粛さに触れます。それまで「神様なんかどうかしら」といいかげんに考えていた者に、畏敬の念が生じる。「おそれの念」とは、単に恐ろしいという意味ではない。これは、神は実在の神である、厳粛な神であると示される、ということです。
どうしてそうなったかというと、奇跡としるしが伴うからです。「奇跡」とは「τερατα テラタ 不思議」という字です。「しるし」とは「σημεια セーメイア」で、目に見えない何かがあると示すものです。神は目に見えない御霊ですが、霊は見えないからといって軽んじ、侮るべきではありません。神がないもののように思っていると、大変なことになります。不信仰なことに対する神の裁きは厳粛です。私たちは、襟(えり)を正して信仰をしなければなりません。
ここで、信者同士が皆、しょっちゅう家に集まった、とある。まあ、500人、3000人というように急に膨張しましたから、全員が一緒に集まるなどということはなかったでしょう。しかし、お互いが家々に、”家のエクレシア(注2)“といいますか、家の教会に集まっておったのが、初代教会の姿であります。今までの神殿や会堂の宗教ではなく、家庭の宗教、家庭の集会、家庭単位の集会がいよいよ広まっていった模様を、ここに書いてあるのです。
宗教というと、何か一定のシナゴーグとか教会堂に行って礼拝する。それが敬虔な姿と思うときに、そうではない。ペンテコステは、教会堂や神殿から宗教を家庭に奪い返すことであります。皆が家庭で集会をするということが始まった。坊主や牧師が宗教を専売特許のように独占しておる時に、聖霊に満たされた者たちがそれを奪い取って、そして家で集会をする。これが原始福音の姿であります。
どこかにある会堂が聖(きよ)い所だと思うべきではない。各家庭に皆が集まって、パンを割き祈りをした、とあります。イスラム教徒は、聖地といえばメッカであり、メッカの方に向いてお祈りをします。聖地はあっちだ、神様はあっちだと思っている。そんな宗教の考え方から解放するのがペンテコステです。各家庭が聖所です。否、各人が聖霊の宮である。「あなたがたは神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか」(コリント人への第一の手紙3章16節)と、パウロも言っているとおりである。私たち個人個人が贖われるばかりでない、家庭も礼拝する場所となる。
教会堂で祈ることが礼拝だと思っているようなクリスチャンには、どうしても、家庭で充実した宗教生活が送れない。家庭は家庭、教会は教会といって区別します。教会堂を出た途端に、もう信仰が失われる、薄まってゆく。
しかし、私たちにはそのような教会堂はないんですから、各家庭が一番の祈りの場所、礼拝の場所、神を崇める場所でなければならない。また、各家庭において神が崇められてこそ、本当の宗教であるといえます。お宮やシナゴーグから、各家庭に宗教を奪い取らせるようなエネルギーが突き上げてくる。これがペンテコステであります。
その意味において、キリスト教徒が十分、家庭で信仰生活を活かしているでしょうか。
それは一つには、ほんとうに心を集中して祈る場所がないんですね。特にアパート生活などになりましたら、食堂も居間も寝る所も一つで、どうも聖別された場所がないように感ずる。それは人間の心の中に、聖別ということがないからです。しかし、せめて大きな家に住む人は、祈りの密室が欲しいものです。
その意味で、昔から日本では家に仏壇や神棚がありまして、そこに手を合わせたものです。私は、これはいい風習だと思います。宣教師や牧師は、「仏壇を壊せ、偶像を引きずり下ろせ」と言います。それはそうだけれども、ではそれに代わる、何かもっと積極的なことがないならば、私たちの心の隙(すき)に、目に見えぬ偶像、神ならぬものが入り込んできて、占領してしまいます。祈る場所を家庭にもたないことになれば、もっと悪いと思います。
(注2)エクレシア
口語訳聖書では「教会」と訳されているが、本来はギリシア語で、「呼び出された者の集い」の意。ヘブライ語の「カハル(会衆)」に当たる。
形ではなく、まず祈ること
キリスト教が、なぜ日本人に根を下ろさないか、家庭に根を下ろさないか。それは、家庭における宗教生活、祈りの生活を軽んずるからです。
明治期に多くの孤児たちを養い、「孤児の父」といわれた石井十次先生は、祈りの人でした。ひざまずいて祈っていた部屋の畳がすり切れるほどだった。一里四方に聞こえるほどの声で祈られたら、奇跡的に導かれたという。しかし病身でしたから、よく布団をかぶって寝ておられる。そんな場合どうやって祈っていたかというと、臥禅(がぜん)ということをしました。臥禅とは寝た姿勢でする禅ですが、そのようにして祈ったことを日記に書いています。
私も朝、夜、よく臥禅して祈ります。皆さんがこの習慣を身につけられると、だれでも祈ることができると思います。祈り心地で休み、祈り心地で目覚める。
「そんなふうに祈るのは不謹慎だ」と言うなかれ、です。威儀を正して正座して祈るだけが、祈りではない。自分に適した祈り方があります。もし朝、目が覚める時も、寝たまま祈り心で、「ああ、神様、生きていました」と、生かされている感謝と共に目が開きますと、そのまま祈りになれます。また夜、殊さらに言葉に出さずとも、祈り心で1日を感謝して眠る。これならだれでもできます。こういうことさえもしないならば、家庭で祈りの生活をすることは、都会のアパート生活時代になると、いよいよ難しくなると思います。
病院において病人は、寝たまま祈り心でなければどうやって祈れますか。祈るためには手を上げるのがいい、いや手を合わせるのがいいなど、いろいろ祈る姿勢について言われますが、イエス・キリストにおいて祈りの姿は自由でした。十字架の前夜、ゲッセマネの園においては、イエスは大地にうつぶせになって祈られたと書いてあります。
どうか、私たちにとって必要なことは祈ることです。祈りにしがみつくということです。聖霊が、神の霊が私たちに臨み、満ち満ちてきますと、もうじっとしておられず、祈らずにおれなくなります。これは大きな変化だと思います。今までは祈ることが義務的であったのに、祈りが楽しくてうれしくてたまらなくなる。
どうぞ、心から祈りとうございます。時々は郊外に出て、山奥で、あるいは密室で、声を張り上げて、ご自分の運命を変えることのできるお方に寄り頼んで祈ることが大事です。神は生きていましたまいます。(一同激しく祈る)
まず祈ることは、神の御霊の光に照らされ満たされることです。しかし、それだけではいけません。なすべきことを教えられ、導かれ、問題の解決を具体的に訴えることが大事です。自分にこうしてください、あの人がこうありますように、あの方が救われますようにと、祈りは具体的でないといけません。神様は、自分のなすべきことを具体的に示したもうものです。このように、具体的な信仰をもちとうございます。耳で聞く信仰でなく、目でしるしを見たてまつる信仰をもちとうございます。これが原始福音です。
「全能の神様、あなたが問題にタッチしてくださったら、これはできます!」と言って、神の力に寄り頼む。わが力ではできないことを願うんです。どうぞ、祈ってください!
(1970年)
本記事は、月刊誌『生命の光』869号 “Light of Life” に掲載されています。