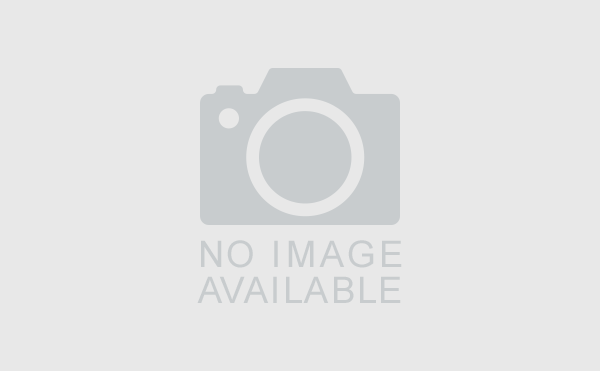聖書講話「塵をかぶって仕える喜び ー祈りの宗教生活(前編)ー」使徒行伝2章37~40節
聖書には「悔い改め」という言葉がありますが、これは道徳的な失敗を「後悔する」ことだけではありません。それまで神を信じられなかった者が、神の霊、聖霊を受けて、心が引っ繰り返り、喜ばしい人生を生きはじめるという、内面の大転換をも指しているのです。
聖霊を受けた後に、何が大事かを、使徒行伝2章のペテロの言葉から学びます。(編集部)
ペンテコステ(注1)の日に聖霊を受けた使徒ペテロは、11人の弟子と共に立ち上がって、集まった多くの人々に、ユダヤ人たちが十字架につけたイエス・キリストを神が復活させられたことを、雄々しく語りました。その時に、多くの人が心を刺されました。
人々はこれを聞いて、強く心を刺され、ペテロやほかの使徒たちに、「兄弟たちよ、わたしたちは、どうしたらよいのでしょうか」と言った。すると、ペテロが答えた、「悔い改めなさい。そして、あなたがたひとりびとりが罪のゆるしを得るために、イエス・キリストの名によって、バプテスマを受けなさい。そうすれば、あなたがたは聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は、われらの主なる神の召しにあずかるすべての者、すなわちあなたがたと、あなたがたの子らと、遠くの者一同とに、与えられているものである」
使徒行伝2章37~39節
私たちが罪(犯罪という意味ではなく、神から離れた状態。また、それによって生じる道徳的な間違い)を赦(ゆる)されるためには、ただ、自分は悪かったと悔い改めるだけではいけません。それに伴う聖霊のバプテスマ、聖霊の賜物を受け取ることが大事です。ペンテコステの日に起きた霊的な出来事の、究極の目的と意味は、このペテロの言葉にあります。
今の西洋流のキリスト教では、自分は道徳的に悪いことをしたといって、ただ罪を悔い改めることを「悔い改め」と思われています。だが、聖書の言う「悔い改め μετανοια メタノイア」 とは、”回心”であり、聖霊の賜物を受けるということに基づくのです。「聖霊のバプテスマを受ける」ことと、「キリストを信ずる」こととは、表裏の関係にあります。
ですから使徒パウロは、エペソの町に行きました時に、「あなたがたは、信仰にはいった時に、聖霊を受けたのか」(使徒行伝19章2節)と尋ねております。「聖霊を受ける」ということと、「信ずる」ということは、初代教会においては一つの出来事の両面だったからです。
しかし、「そのような聖霊の賜物はもう必要ではない」などとキリスト教内でも言う人がいますが、決してそうではありません。39節に「この約束(聖霊の賜物の約束)は、われらの主なる神の召しにあずかるすべての者、すなわちあなたがたと、あなたがたの子らと、遠くの者一同とに、与えられているものである」と書いてあります。原文は「遠くの者一同」ではない、「遠くの者すべてに、どんな遠くに住んでいる者でももれなく」です。
また「神の召しにあずかる」という字は、「神に呼ばれる」というギリシア語です。このペンテコステの約束は、主が呼び寄せられるすべての者に対する約束であります。
それで、聖霊の賜物が与えられる、聖霊にバプテスマされるということは、主が召したもうた、選びたもうた、呼び寄せたもうたことの証拠であります。
多くの人は、「自分はクリスチャンになろうと決心した」などと言って、人間の決心でキリスト教に入ります。また「自分は伝道者になろうと決心した。それで神学校に行こう」と言います。けれども、神が召しておられないのに決心しましても、それは偽りです。
聖書には、神が呼び寄せたもうた者にはだれでも、共通な約束の成就、すなわち聖霊の賜物が降(くだ)る、とあります。我らの神、主が呼び集められる者はだれでも、どんなに遠く離れている人々に対してでも、もれなく適応されるのだ、とペテロは言いました。

(注1)ペンテコステ
ギリシア語で「第50」を意味する言葉で、ユダヤ教の三大祭りの一つ、「七週の祭」のこと。過越の祭から50日目に当たる、春から初夏のころに祝われる。五旬節とも。キリスト教では聖霊降臨の時とされる。
すべての者、選ばれし者
こうしてペンテコステの結論を書いてあるわけですけれども、私たちはここに救いを見いだすのです。もし、ペテロやヨハネほかイエス・キリストの直弟子、十二使徒と呼ばれた人たちだけに、聖なる力、聖霊が降ったのであるならば、ほかの者たちにはさびしいことです。しかし、120人の者一同に聖霊が注がれた、といいます。そこには、女や子供もいた。「ベザ写本」という古い聖書の写本には、1章14節に「子供たちも(共にいた)」という部分があります。
イエス・キリストは十字架にかかり亡くなったがよみがえられ、多くの人が復活のキリストを見ておりました。その数は500人以上であったと、パウロはコリント人への第一の手紙に書いております。しかし、復活のキリストがもちたもうた御霊を受け取った者は120人でした。ここに厳しい審判があります。
キリストを慕う人たちは多くいました。その中で、聖霊を注がれたのは120人であった。12人のみではなかった。ここに、私たちに救いがあります。また厳しさもあります。だれでも彼でも、クリスチャンに注がれるのではない。500人のうち、神の霊が乗り移った人は120人であったというとき、私たちはその120人に数えられとうございます。
神の霊は、篤信な人に注がれるとはかぎらない。ある階級の人たちにしか注がれない、というのではたまりません。もう20年前(1950年)のこと、私たち幕屋の小さな群れに神の御霊が臨みました。その後、ある教会の牧師がやって来て、しみじみと「ぜひ自分もそうありたいと願う。どうしたらいいか」と言いますから話を聞きますと、こうです。
私たちの集会に、あるミッション・スクールに通っている一人の女学生がいましたが、彼女がその牧師の担当している「聖書の時間」に、真ん前で顔輝かせ、目を光らせて聴いている。すると、牧師は話ができず、ごまかしが利かなくなる。
それで、「あなたはどうしてそんな光った信仰をもっているのか」と尋ねると、「私はある時、阿蘇での手島先生の聖書講筵に行って聖霊を注がれました。そうしたらほんとうに変わりました」と言って、その女学生が次々と不思議な話をする。それで自分も、ぜひそうありたい、というわけです。私は「断食してでも祈ったらいい。神様は必ず恵んでくださいますよ」と申し上げました。
しかし、その後お会いした時には、「私のように長い間、牧師として忠実に奉仕した者が聖霊を頂かずに、そうでない、まだ小娘にすぎない者が聖霊を頂くなんていうことは、考えられん。また、私の家内は医者であるが、医学も捨てて牧師の妻になった。こういう夫婦が恵みからもれるということはおかしいし、神様があなたがただけに聖霊を注いで、我々に注がんというのにも矛盾があると思う。結論するのに、あなたがたの信仰はおかしいんだ」と、夫婦で相談のうえ、そういう結論になったと言うんです。
だが、使徒行伝2章には、男や女の奴隷たちでも、最もみすぼらしい無学な教養のない、卑しめられた階級の者にも、神の御霊が注がれる日が来る、これがペンテコステである、と書いてある。どうしてこの人はそういうことを言うのだろう。ここに、牧師とか伝道者とかいう者の驕(おご)りがあります。自分は伝道者である、牧師である、と思っている。こういう宗教的特権階級を排除する! これがイエス・キリストの福音である。ペンテコステの出来事である。ひとしく聖霊が120人の者に注がれたのです。
埃の中を通る奉仕
ペテロたちが使徒と呼ばれたように、専心伝道する人が必要ではあります。しかし、その人たちが誇ることはありません。神に賜物を注がれた者は、ひとしく同じだからです。
聖霊はある意味では、私たちを無差別に取り扱ってくださる。しかし、ある意味では、差別がありました。500人の人たちがキリストを慕っていましたが、恩寵(おんちょう)から、恵みからもれる人たちがあったということも事実です。先ほどの牧師のような人であっても、です。
英語で牧師のことを「minister ミニスター」といいます。大臣のことも、同じくミニスターといいますね。アメリカでは、牧師が「自分はミニスターです」と言えば、飛行機の切符でも汽車賃でも、またデパートでも1割ぐらい値引いてくれます。こういう特権階級があります。これがミニスターというものです。
しかし「minister」というのは、もともとは「奉仕する」という言葉です。奉仕する者が大臣になったり、アメリカの牧師のような特権を社会的に認められるようになったりしたら、これはおしまいですね。教会では、牧師や伝道者の務めを聖職といいます。そして、我々のような者を、俗人、平信徒といって低く見ます。
私は、自分も受けたペンテコステの霊のゆえに、これに「ノー!」と言いつづけてきたんです。もし、伝道ということを職業にしはじめたら、そこに堕落があります。その間において、伝道者に特権が認められたら、宗教は堕落します。
使徒行伝に何度も出てくる「奉仕」という言葉は、ギリシア語で「διακονια ディアコニア」といいます。「δια ディア」とは「~を経由する、通る」で、「κονια コニア」は「埃(ほこり)、灰、石灰」という意味です。すなわち、本当の奉仕は「埃の中を通る」ということなのです。
私は先週、岡山に行ってきました。岡山には、明治・大正年間に「孤児の父」といわれた石井十次先生の始められた孤児院がありました。先生はただ神に祈りつつ、3000人もの気の毒な孤児を救済した、キリストの聖者です。石井先生は明治22年(1889年)、岡山の医学校を卒業直前に辞めて、一生を孤児のために生きようとした時に、日記にこう書いておられます、「神様、世の中の名誉、安楽の道を絶って、あなたのために雑巾(ぞうきん)となって働くことを決しますゆえ、常に聖霊の御手をこの僕(しもべ)に置き、あなたの御用に勤めしめたまえ」と。こういう言葉こそ、このディアコニアの意味だと私は思うんです。
埃をかぶって生きる、塵(ちり)をかぶって生きる人生。これを決意し、実行することが、本当のディアコニア、奉仕という意味なのです。奉仕する者が、ミニスターになって「大臣」などと言われると、「おお!」なんてこたえて威張るんだったら、これはもう、漫画よりも滑稽(こっけい)です。そうじゃありませんか。黙々として一生、埃をかぶって生きることのできる者、これがキリストの弟子であります。
なかなかこういうことはできませんね。だが使徒行伝を読むとわかりますように、聖霊が、神の御霊が臨んだ時に、自分を忘れて、埃をかぶって仕えてもうれしくてたまらないような、喜びの生涯が始まるのです。大きな喜びのゆえに、神が与えたもうた聖霊の賜物のあまりの素晴らしさのゆえに、自分の社会的な地位や身分、家柄がどうであれ、埃をかぶって生きる、我を忘れた生涯が始まります。これがペンテコステで起きた出来事です。
ですから、ペンテコステ派という教派の人たちが、「ペンテコステにおいて異言(いげん)が語られた」ということだけを強調し、それを特徴としているならば、これは大きな間違いです。
今、私のところで働いている十数人の男女の青年たちも、もう身を粉にして、塵をかぶるようにして生きてくれています。ディアコニアという言葉を、目に見えるように生きている。こういうことは躾(しつ)けてできることではありません。塵をかぶっても悔いのないような、大きな感激がそうさせるのです。聖霊の賜物が注がれると、私たちはそうなるんです。
曲がりくねった時代
ペテロは、ほかになお多くの言葉であかしをなし、人々に「この曲った時代から救われよ」と言って勧めた。
使徒行伝2章40節
この箇所には、聖霊を注がれた後のあり方が書いてあります。「時代」はギリシア語の「γενεα ゲネア 世代、同時代」という語で、英語の「generation ジェネレーション 世代」のことです。「曲った」 は、ただ曲がっているだけでなく、曲がりくねった、不義な、という意味です。
曲がった時代から救われる、ということは何でしょうか。自分自身が救われずに、曲がった時代から救われるということはありません。
私たちが聖霊に満たされてみると、まず何を感ずるかというと、「この時代は曲がっている」ということです。この時代はほんとうに曲がりくねった、間違った時代と感じます。今のキリスト教は、この時代に溺(おぼ)れ、この時代の寵児となろうとしております。しかし、このジェネレーション(時代)は曲がっておりますから、没落しゆく世の中で、寵児となろうとするならば、これは大きな間違いです。
救われてみますと、この現代に対して抵抗を感ずる。「今まで自分も、世の人々も間違っていたなあ」と言って、いかに自分たちが曲がりくねった、間違った社会に生かされているかに驚きます。このような反抗心がわき上がってくる。
今の人は、「戦争反対、平和、平和」と言います。そのように「平和」を唱える反戦団体の人たちが、今朝も早くから代々木公園にたくさん集まって、「安保条約反対!」(注2)などとガヤガヤやっています。全然、平和な雰囲気ではないですね。現代の資本主義文明も曲がっているかもしれないが、それを逆に曲げようとしているのを見ると、この聖書の言葉は「曲がり”くねった”時代」と訳したらもっとふさわしいですね。彼らのすることは、「曲がりを直そう」じゃない、もっと破壊して曲げに曲げようとすることにしか見えません。
現在、安保条約が盛んに政治問題になっています。私は単純に賛成でも、反対でもありません。えらい困ったことだと思っている。日本を仮想敵国にするような国もある国際環境の中で、ただ理想だけ唱えても駄目です。せっかく日本は平和憲法を掲げて、内村鑑三先生が夢みたことが実現するかに思えましたが、周囲が許さないですね。中国、ソ連が許さない。またアメリカが、その他の国々が許さないですね。日本はその間に挾まって、左するか右するか、中立ということも難しい。曲がりに曲がった状況です。
このような曲がりくねった時代から救われることが、私たちの救いです。現代の政治を、国際危機を、どうでもいいというのではありません。国際的な緊張や矛盾は、人間の力だけでは解決できない。聖霊にバプテスマされた救いの喜びが、それを超えしめる。この曲がった時代は滅んでゆくでしょう。私たちは滅びないものに錨(いかり)を下ろしとうございます。
(注2)70年安保闘争
戦後、連合国軍の占領の終了とともに日米間で結ばれた日米安全保障条約の更新を阻止するために、全共闘などの学生を中心として行なわれた運動。各地で、火炎瓶やゲバ棒で武装した学生たちと、警官隊とが衝突した。
御霊が断絶を超える
使徒行伝2章17~18節に、ペテロが預言者ヨエルの言葉を引いて語っています、「神がこう仰せになる。終わりの時には、わたしの霊をすべての肉なる者に注ごう。そして、あなたがたの息子、娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には、わたしの男奴隷、女奴隷たちにも、わたしの霊を注ごう」と。
若い青年時代は敏感に、時代の曲がりくねっているのに対して、反感、抵抗を感じます。しかし、老人は「まあまあ」と言いやすい。保守的です。宗教というものが、老人に握られてしまいますと、どうしても今までの慣例儀式を守りつづけることに終わります。
だが、ペンテコステにおいて何が起きたか。若者たちは幻(ビジョン)を見て、理想に向かって進む。また、老人たちは夢を見る、霊夢を見る。預言的なことですね。超理性的な経験をもつに至る。こういう社会が生まれてきます。新しい時代が生まれることを皆の人が求める。ここにおいて、老人のもつ夢と若者の幻(ビジョン)とが違うかもしれないが、しかし一つ御霊が、年取った者の古い経験を活かすように、また若い者の進取的な希望を活かすように、それぞれ働いてくれる。ぺンテコステは、すべての者を一つにし、若者にも老人にも、男にも女にも大きな刺激を与えます、奮起させます。このことが大切です。
初代教会当時、一般的に女性の社会的地位は非常に低いものでした。圧迫されていました。しかし、ペンテコステの御霊が臨みました時に、女性はそのような圧迫を、塵灰(ちりはい)をかぶることを物ともせず、立ち上がることができました。ここに、男女の性別を超えて一つに生きる喜びがあります。ペンテコステは、そのような力を生むものです。
もし私たちの集会が、老人ばかりになったならば、これはペンテコステの霊が消えたからです。また、女の人ばっかりになって、男は少しで、隅っこに窒息しているのであるなら、これは何かが足りないからです。
男が奮起するもの、これ原始福音です。弱い弟子たちが立ち上がったように、聖霊が臨む時、私たちは恐れを知らない人間になれます。これが宗教の役割です。原始福音の伝道は、男の活躍舞台です。女の人たちには悪いけれども、私はそう思っているんです。
ペテロが、預言者ヨエルの預言を引いてペンテコステの現象について説明したように、若者たちは革新的な情熱をわかすことができます。それが原始福音です。また、お年寄りにも本当の宗教の醍醐味を満喫せしめてくれるもの、これ原始福音であります。
この間、新聞を読んでいたら、一つの教会の中で保守派と過激派というか、右と左とが互いに訴え合い、同じ教会堂で別々の祈りをしているといいます。なぜ、そうなるのか。これは、人間が中心だからです。それぞれ自分が中心だからです。
だが私たちのように一つ御霊が、神の霊が臨んで支配する現象がある。これを原始福音といいます。一つの圧倒する霊が、人々の心を占領し、支配し、導くからには、私たちに大きな断絶というものはありません。
このようにすべての者が、男も女も、奴隷の男女も、無学な卑しい階級の者も、御霊を注がれる。ユダヤ人のみでなく、遠い所に住む者――私たちのように極東といわれる所に住む者にも、この約束は通じる。「遠い所」とは、空間的にも時間的にもです。ほんとうにありがたい約束だと思います。思い切ったことを、2000年前、漁師のペテロが言ったものだと感心します。神の霊が言わしめたとしか思えません。(後編に続く)
(1970年)
本記事は、月刊誌『生命の光』868号 “Light of Life” に掲載されています。