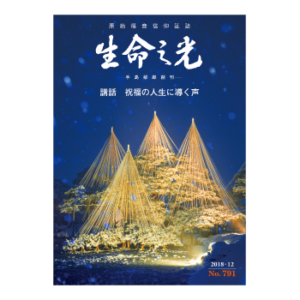聖書講話「祝福の人生に導く声」ヨハネ福音書10章1~11節
今日は、ヨハネ福音書10章1節から学んでまいります。これは、イエス・キリストが「わたしはよき羊飼いである」と言われた有名な箇所です。
よき羊飼いの譬え
「よくよくあなたがたに言っておく。羊の囲いにはいるのに、門からでなく、ほかの所からのりこえて来る者は、盗人であり、強盗である。門からはいる者は、羊の羊飼いである。門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名をよんで連れ出す。自分の羊をみな出してしまうと、彼は羊の先頭に立って行く。羊はその声を知っているので、彼について行くのである。ほかの人には、ついて行かないで逃げ去る。その人の声を知らないからである」。イエスは彼らにこの比喩を話されたが、彼らは自分たちにお話しになっているのが何のことだか、わからなかった。
(ヨハネ福音書10章1~6節)
イスラエルという国のあるパレスチナ方面では、昔から遊牧が行なわれています。それで、イエス・キリストが羊のことを譬えにして話されると、私たち日本人にはピンときませんが、そこに住む人々にはよくわかります。
ここで「門」とありますが、野原のあちこちを移動して羊の群れを飼っていると、夜になったら家に帰ることができない。そういうとき、狼や山犬から羊を守るため、野原のところどころに土手で囲いが築いてあり、そこに羊を追い込んでおきます。その囲いの門のことです。
朝になったら、羊飼いが羊を呼び出します。羊は自分の羊飼いの声を知っていて、呼ばれるとやって来る。しかし、そうでない者がどんなに呼んでも、羊は来ません。こういうことを譬えにして、イエスはキリストとその民との関係をお語りになりました。

誰が真理を聞きうるか
ここでイエス・キリストは「羊は羊飼いの声を聞く」と言われています。この時もたくさんのユダヤ人たちが、キリストを取り巻いていたでしょう。しかし、キリストがほんとうに弟子であると思われる者は、羊が羊飼いの声を聞き分けるようにキリストに聞き従う。そうでない者は側にいて聞いていても、その深い意味がわかりません。ここに宗教を説く難しさがあります。
仏教の禅宗には、次のような話があります。釈迦がインドの霊鷲山(りょうじゅせん)という山で説法の会を開きました。ところがその時、何も言わずにただ一輪の花を拈(ひね)って見せた。皆、ただ黙って見ていたが、迦葉(かしょう)という弟子だけがにっこりと微笑みました。それを見て釈迦は、「われに微妙(みみょう)の法門あり。不立文字、教外別伝、摩訶(まか)迦葉に付嘱す」と言いました。「微妙の法門」、人間の知恵や知識では至ることのできない不思議な智慧、言葉では説くに説けない真理を、迦葉ただ1人が悟ったのだ、というのです。釈迦は何も語りもせず、一輪の花を示しただけです。他にも優れた弟子たちが一緒にいたのですが、釈迦は迦葉に法統を継がせました。
このように、「声を聞く」というのは、ただ言葉を聞くというだけのことではなく、その心を読み取るということです。
イエスは後の箇所で、「わたしは門である。わたしをとおってはいる者は救われるであろう」(9節)と言われています。天の生命には、イエス・キリストを通らなければ入れない。多くのクリスチャンはこの言葉を読んで、キリスト教を信じ、教会に行きさえすれば救われるように思っているかもしれません。しかし、当時もたくさんの弟子たちが取り巻いていたでしょうが、「わたしの羊はわたしの声を聞く」と言われるイエスの言葉を聞いて、心底から頷くことのできる、本当のキリストの民は少なかったのです。
知音の心
3節に「羊は羊飼いの声を聞く。そして彼は自分の羊の名をよんで連れ出す」とあります。私は信仰を求めて来る人に、やかましく言う場合があります。それは、私は宗教的な生命を伝えようとしているけれども、信仰上の私の問いに対して、ただ表面的な言葉のやり取りをしてしまうからです。宗教を学ぶというならば、私が「こう」と言えば「ハイ」と応えるような、当意即妙の境地でなければだめなのです。「羊は羊飼いの声を聞く」とは、そのような境地です。
親しい仲でしたら、「オイどうだ」「ウンウンやっとるよ」「そうかい、それはよかったねえ」で通じるものです。隣で聞いていたって、何のことかわかりません。しかし、お互いの間では通じているんですね。こういう世界を、音を知る、「知音(ちいん)」といいます。
昔、支那に伯牙(はくが)という琴の名手がおりました。その友人に鍾子期(しょうしき)という人がいて、伯牙の演奏の心をよく知っておりました。伯牙が中国の聖山である泰山を思って琴を弾くと、鍾子期はその音を聞いて、「巍巍乎(ぎぎこ)として太山のごとし(高くそびえてまるで泰山のようだ)」と即興で詩を吟じました。また、流れる水を思って弾くと、「湯湯乎(しょうしょうこ)として流水のごとし(まるで川の水が勢いよく流れるようだ)」と詠いました。そのように、伯牙の琴の音を聞き分けることができました。
だが鍾子期が死んだ後は、「世の中に琴を聞かせるに値する人はもういない」と言って、伯牙は琴を壊して弦を断ち、再び琴を弾かなかったといいます。「知音」という言葉は、この故事に由来しています。宗教において大事なのは、この知音の心です。
確かな実在に入るには
そこで、イエスはまた言われた、「よくよくあなたがたに言っておく。わたしは羊の門である。わたしよりも前にきた人は、みな盗人であり、強盗である。羊は彼らに聞き従わなかった。わたしは門である。わたしをとおってはいる者は救われ、また出入りし、牧草にありつくであろう。盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするためにほかならない。わたしがきたのは、羊に命を得させ、豊かに得させるためである。わたしはよい羊飼いである。よい羊飼いは、羊のために命を捨てる」
(ヨハネ福音書10章7~11節)
イエス・キリストは、「わたしは門である。わたしをとおってはいる者は救われ、また出入りし、牧草にありつくであろう」と言われています。そのように、緑のオアシスに導かれてゆこうと思うならば、たとえ死の陰の谷を歩いても、羊飼いに、キリストに従ってゆくことが大事です。
はるか彼方にオアシスのような豊かな祝福があるということはわかるけれども、そこまでの道のりは砂漠の旅かもしれません。それでもキリストに頼り、ついてゆくという心があるなら、ついにそれを発見します。これは、羊が羊飼いの声に従っていれば緑の草にありつけることを知っているように、私たちもキリストを通ってゆけば、最も真実な世界に導かれるという確信があればこそです。
「わたしは門である」とあるが、ユダヤ人の宗教哲学者マルチン・ブーバー(注1)*は、「信仰は人間の心の中に生ずる感情ではなく、リアリティー、確実なる実在への入り口である」と言っています。
は、「信仰は人間の心の中に生ずる感情ではなく、リアリティー、確実なる実在への入り口である」と言っています。
これは私たちが信仰を学ぶにおいても大事なことです。私たちはただ心の中で、「宗教はいいもんです。法悦の気持ちに浸って嬉しいもんです」といって、何か1つの宗教的雰囲気を楽しむために宗教を志しているのではない。現実にありありと全宇宙を支えている確かな実在である神の霊、神の生命に触れるためです。だが、神の生命には、私たち人間は信仰によらなければ触れることができません。信仰によってそれに触れればこそ、法悦の喜びもあるけれども、それは結果なのであって、まず大事なことは、確かな実在との接触に私たちが入ってゆくことであります。
(注1)マルチン・ブーバー(1878~1965年)
20世紀を代表するユダヤ人宗教哲学者。『我と汝』を著して、聖書の思想を土台とする「対話の哲学」を提唱。ユダヤ教の神秘主義的革新運動であるハシディズムを世界に紹介した。
実在に寄り頼む信仰
そのような実在に触れる経験なしに「神があるか、ないか」などと、どれだけ考えてもわかるものではありません。「神とは〇〇だ」といういろいろな説明を信じたとしても、それは説明であって私たちの救いにはなりません。頭ではわからないけれども、確実に私たちの救いの力であり、生命であるお方に触れていることと、「神とはこういうものである」という説明を一生懸命信じたり、教理を信じたりしていることとはだいぶ違います。
だから、教理を信じているような人の信仰は、何かが起こるとすぐにぐらつくけれども、確実な実在に寄り頼んでいる人の信仰はぐらつきません。他の人がぐらついたって、何が起こったって神を信じようと思う。ここに、信仰に2つのタイプがあることがわかります。本当の実在、リアリティーに触れている人と、神についての仮説を信じている人との違いが出てくるのです。
4~5節に、「(羊飼いは)自分の羊をみな出してしまうと、彼は羊の先頭に立って行く。羊はその声を知っているので、彼について行くのである。ほかの人には、ついて行かないで逃げ去る。その人の声を知らないからである」とあるように、羊と羊飼いの間に真実な関係、愛の関係があるということがわかります。
ある時は、羊飼いが死の陰の谷に連れてゆくようなこともあるでしょう。砂漠では陽が照りつけて、行けども行けども水にありつけないこともあるでしょう。しかし羊はついてゆく。その声を知っており、全く信頼しているからです。神と私たちの関係もこれと同様です。
こういう確かな声に導かれているかどうか。導かれていない信仰というのは、実にあやふやです。それで、「ああでもない、こうでもない」といってうろうろしている。結局、神がよくわからないから、自分に寄り頼んで自分で暴走し、失敗する。ところが、ほんとうに神に聞く者の信仰は強い。何も理屈がない。けれども、確実である。これは、私たちが信仰を学び求める場合に大事なことです。
出会って知る神
神は絶対者で、最も大いなる者ですから、人がこれを説明しても説明しきれるものではありません。それで神の霊に出会ったことのない人にとっては、神の名を呼ぶことは非常に難しいです。
私の父は晩年にキリストの信仰に入りましたが、私の集会に出席するようになって間もなく、「神とはいったい何だ」と言います。それで、「お父さん、あなたはお祈りする時、どう言って祈るのですか」と聞きました。すると父は「実は、『神よ』と言ってもどうもピンとこない。聖書に『神は光である』と書いてあるから、『神様、御光様、世の光である者よ、宇宙の光よ』と呼んで祈っているが、どうだろうか」と言います。
「それでも祈らない人よりはいいでしょう。しかし、『御光様』と言うのでは、神を親しく感じながら祈るという気持ちにはなりにくいでしょう」と言いますと、父は「そうだ」と言います。
「お父さん、そこが問題です。神は人格的なものだから、人格的なものに呼びかけるように祈るのがいいでしょう。おおげさな形容詞は要りません。私はあなたを『お父さん』と呼ぶでしょう。それをもったいぶって、『手島郁郎の生みの親なる父よ』と言ってみたところで妙です。神に祈る場合も同じです。素直に『神様、あなたは』とか、『お父様』でいいんです」と言いました。
しかし、これは私の父だけの問題ではないと思います。信仰が低迷したときなどは、神を身近に感じません。それで、神に対して「お父様、あなたは」と言えません。それは神とその人との間に、羊飼いと羊の間のような愛の関係が成立していないからです。
けれどもKさんのように、中風で足腰が立たず一生ベッドに縛られて生きるはずだったのが、幕屋の集会で救われたという経験。これは確実な贖いの経験です。自分を愛し、救う者が実在する。そのお方に触れて、「ああ、お父様!」と呼びはじめた神は、頭で思索した神とは違います。このような在りて在る神に出会う経験に入らない限り、その人の神は本当の神ではありません。
羊を慈しむ愛
(ヨハネ福音書10章)10~11節で「わたしがきたのは、羊に命を得させ、豊かに得させるためである。わたしはよい羊飼いである。よい羊飼いは、羊のために命を捨てる」とイエスは言われます。多くの人は自分が愛されることだけを求めます。けれども、人を愛さずに愛されることがあるものですか。また伝道するときに、自分が犠牲になることを覚悟しない者に、みんながついてゆくものですか。
先日のこと、西宮の田中俊介さんが、「先生、改めてお願いするが、今日から先生の弟子にしてください」と言われる。「それはまた、どうしてです」と聞きますと、「私は、信仰生活が四十数年になるけれども、いまだ本当の信仰に至っていない。私は若い時から賀川豊彦先(注2)生に愛された者です。賀川先生亡きあとは、日本生活協同組合連合会会長という職を譲り受けてやっております。西宮で1200人の従業員を抱えています。
けれども、従業員に1人のクリスチャンもいない。私だけです。これでは賀川先生に対しても相済まない。このままでは、この協同組合は賀川先生の言われる精神的な協同組合主義ではなくて、唯物主義的なものになってしまいます。これでは堪らないです。自分自身が変わらなければいけないと思いました」と言われます。それで私は、「あなたは今まで、クリスチャンとして戒律ばかりで生きてきたでしょう。それは愛さねばならないという義務としての、倫理としての愛です。私の言う愛はそうじゃない。愛というのは生命の発露です。私は理屈なしに弟子たちがかわいくてしょうがないのです。あなたのように義務で愛された愛など、誰でも嫌です。また、愛さねばならないから愛する、というのは功利的なものを含んでいて、本当の愛ではない。そこがあなたとの違いです」と言いました。
この方は先日、私が大阪の幕屋の方々と熊本の温泉に行って、皆さんの背中を流した話をお聞きになったそうです。私が宗教というものを、聖書講義だけで説くと思ったら大間違いです。皆と一緒に風呂に行き、お互いに裸で語り合いながら、何か感じるものがあって、みんな大いに喜ぶ。これは説明でないものが、私たちの心に通うからです。
結局、「御霊によりて懐(いだ)ける愛」という言葉がコロサイ書1章にあるように、聖霊に触れなければそのような愛は湧いてきません。昔の私は今のようではありませんでした。今は、キリストの民である人たちに尽くすことが、私の喜びとなりました。
(注2)賀川豊彦(1888~1960年)
大正・昭和期のキリスト教伝道者、社会運動家。不遇な少年時代を過ごす中で、キリスト教宣教師に触れ、回心。イエスの歩みに倣い、貧民窟で伝道。その後、貧困や労働の問題に取り組む。日本の生活協同組合運動において重要な役割を担った。
キリストこそ永遠の生命に至る門
神の国、神の霊の世界は実在する。その霊界に出入りする者の生き方、愛、信仰は、実在の神を知らないで「神とは何だろう」と真っ暗な中で模索して、「神は光です、真理です、唯一絶対です」といった定義を信じている人の信仰とは、ずいぶん違うことがおわかりになると思います。実在の神に触れて生きている者の信仰は、いかに周囲がごたごたしようが揺るがない強いものがあります。こういう信仰を得ない限り、信仰は虚しいことです。
なぜ、ある人の伝道は実り、ある人の伝道は実らないのかというなら、私は信仰の違いからくると思います。議論の宗教、議論の伝道は聞いていて嫌です。しかし、実在を知っている人の信仰は単純で、強く訴えてきます。聞いているだけでも魂に強く響いてくるものがあります。これはお互いが大いに工夫しなければいけないことです。もし、現在の自分の信仰が薄弱であると思われるならば、本当のものに触れていないからである。「今までの私の生き方は間違っておりました。努力しても実りませんでした。本当のものを知らなかったからです」と心から祈りたい。

ブーバーが言うように、信仰は確実な実在に触れる入り口です。キリストは「われは門である」と言われましたが、キリストこそ永遠の実在に至る門です。私たちはキリストによらなければ永遠の実在なる神の国に至ることはありません。私たちはキリストの御心を心としたい。だが、それは羊が羊飼いの声を聞くというような微妙なことで、説明で教えるのは非常に難しいです。
私は伝道しながら、そう思います。ある人は理屈を超えて「先生!」といって私の言うことをわかってくださるが、そうでない人もいる。「知音の心」、これが宗教を学ぶ者にとって実に大問題なんです。これは結局、お一人おひとりが心のスイッチを切り替えて、心の関門を越えていただくしかありません。キリストは、「わたしは門である。わたしをとおってはいる者は救われる」(9節)と言われたが、このキリストの御言葉が「然り、アーメン」と魂でわかるならば、もう天はあなたに近い。否、あなたはすでに天に接触しているのです。贖われた者は神の国の雰囲気を味わっています。これは理屈ではない。愛された者の実感として知っております。
前章に書かれているシロアムの池で癒やされた盲人は、人が何と言おうが、「あの人が罪人であるかどうか、私は知りません。ただ1つ知っているのは、私は盲人であったが、今は見えるようになったという贖いの出来事です」と言うとき、盲人とイエスとの間に愛の関係が成立していました。それで、人は躓き去っていったけれど、羊飼いなるイエスとその羊である盲人との愛の関係は揺るぎませんでした。こういう関係を、キリストは羊と羊飼いの例に譬えられたのです。
豊かな生命に与る
どうして、羊飼いと羊との関係が聖書の中で、神とイスラエル民族との譬えとしてあるのか。
イエスは「わが羊はわが声を聞く」と言われます。羊は素直な動物です。けれども頭の悪い動物です。自分で水の飲み場も青草のある所も知らない弱い動物です。そして迷いやすいのが羊です。ただ1つ、羊の取り柄は「従順」ということです。そして、羊飼いの声をよく知っているということです。ですから、羊飼いは羊を思うように導くことができます。私たちも、ほんとうにキリストの御声を聞いて生きる不思議な人間でありたい。
イエス・キリストは「わたしがきたのは、羊に命を得させ、豊かに得させるためである」(10節)と言われる。かりに荒野を通り、死の陰の谷を過ぎ越させてでも、羊飼いであるキリストは私たちを豊かな世界に連れてゆきたいと願っておられるのです。
「豊かな」という言葉は、原文のギリシア語では「περισσο? ペリッソス」といって溢れるような豊かさを意味します。たとえばコップに水を注ぐとき、注ぐだけ注いだらもう入りません。それ以上に水を注いだなら水は溢れます。そのような状況のことです。キリストが与えようとされる生命は、そのような豊かな生命です。キリストは、このような尽きない生命の世界に羊を連れてゆくのがご自分の仕事である、と言われる。私たちもキリストに信じて、そういう所に導かれたい。
大事なことは、困難なことがあり、前途に大きい荒野が横たわっていても、どうぞ思い切ってキリストに従い、キリストと偕に歩くことです。苦しさは増しても、それは私たちがより高きに上る希望となるのです。それをせずに、いつまでも不安がっていても、よいことは始まりません。
キリストに導かれる人生は、なんと幸せだろうかと思います。私たちは羊が羊飼いの声を聞くように、「主よ、御声を聞きます」と従順になって、キリストに従ってゆきとうございます。
(1963年)
本記事は、月刊誌『生命の光』2018年12月号 “Light of Life” に掲載されています。