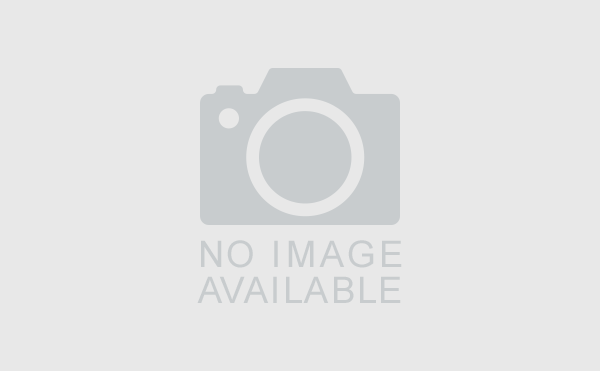聖書講話「主の御前から来る息づきの時」使徒行伝3章12~20節
聖霊降臨(ペンテコステ)の日を迎えた時、イエス・キリストの弟子たちは、約束のとおり、聖なる神の霊にバプテスマ、浸される経験をしました。聖霊が注がれる出来事は、聖書の至るところに記されています。それは、神の生命が怒濤のように流れて、人々の渇いた魂を潤し、息づかしめる経験です。
今回は前回に続き、弟子のペテロが足の不自由な物乞(ものご)いをいやした記事の講話です。(編集部)
使徒行伝3章には、一人の生まれつきの足なえがいやされたことが書かれております。エルサレムの神殿に至る美しの門の前に、足なえの乞食がいた。彼がペテロたちに施しを乞うたところ、ペテロが「金銀はわれになし。されどわが持てるものをなんじに与う。ナザレのイエス・キリストの名によりて歩め」と言うと、立ちどころに躍り上がって歩きだした。
こういう不思議なことが、聖霊に満たされた人の周囲にはしばしば起きるのです。人々は、それを「奇跡」と言って不思議がりますが、聖霊に満たされた人間にとっては、案外、奇跡ではないのです。私においても、祈ってあげますと、死ぬような病気が治ったり、足なえが立ち上がったり、盲人の目が見えだしたりします。あまりにその例が多いから、別に奇跡とは思っておりません。むしろ、「ああ、私に伴ってくださるキリストがお働きになったから、こういうことが起きたんだなあ」と、主の御名を賛美するだけのことです。
だが、こういう宗教経験をもっていない人には、それこそ全く考えられぬ出来事ですから、「奇跡」という名で呼び、「不思議だなあ」と訝(いぶか)ります。
この聖書の箇所でも、人々はそう思ったとみえます。驚いた人々は、ペテロとヨハネが、歩き回っている足なえだった男と共にいる所に集まってきました。それに対して、ペテロは言いました。
ペテロはこれを見て、人々にむかって言った、「イスラエルの人たちよ、なぜこの事を不思議に思うのか。また、わたしたちが自分の力や信心で、あの人を歩かせたかのように、なぜわたしたちを見つめているのか」
使徒行伝3章12節
このような出来事が起きた時に、人々はいやしを行なった人を神のごとくに敬います。また、少しばかり不思議なことが起こりますと、もう天狗になってしまう伝道者がよくおります。しかし、ペテロやヨハネの信仰は違っておりました。自分の力や自分の信心で、何ができるものか! これはキリストがお働きになったんだと言って、はっきりとその不思議な出来事の秘密を話しております。
病のいやしが行なわれると、それは神の証しになります。神様がその人を愛して用い、器としておられることは感謝すべきです。だからといって器が威張ったらおかしい。自分はこんないやしをしたんだ、と吹聴するならば、その人の名は上がるかもしれませんが、キリストはたたえられない。それでは、キリストの本当の僕(しもべ)、弟子であるとはいえません。
ペテロたちは「これは神の栄光が現れたのだ」と人々に説明しています。否、そういう信仰のタイプの人であればこそ、神の霊も働くのです。
ある注解書には、ペテロやヨハネが謙遜して言っている、というように書いてありますが、そうではない。今のクリスチャンのように、謙遜ぶっているのではない。真実、自分はつまらぬ男だと思っているんです。だから彼らは、「どうして私を見るのか。私を見たって、ただの人間に何ができるものか」と、逆に見つめている人々を訝っております。
いのちの君、イエス・キリストの御名
「アブラハム、イサク、ヤコブの神、わたしたちの先祖の神は、その僕イエスに栄光を賜わったのであるが、あなたがたは、このイエスを引き渡し、ピラトがゆるすことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなたがたは、この聖なる正しいかたを拒んで、人殺しの男をゆるすように要求し、いのちの君を殺してしまった」
使徒行伝3章13~15節
「神は、その僕イエスに栄光を賜わったのである」。「栄光を賜わる」とは、神が臨在したもうて、美しの門であったような素晴らしい出来事を起こさしめることをいいます。
「(イエスに)栄光を賜う」という箇所は、「栄光をあらしめる」とか「栄光をもって包む、着せる」と訳すべきです。外套(マント)が身体(からだ)を包むように、神の栄光が包んでいるような不思議な人間、神の栄光が覆い、宿っているような人がイエスでした。ですから俗人の目にも、キリスト――神の栄光をもって包まれている人――の状況はわかっていたのです。
しかし、「あなたがたは、この聖なる正しいかたを拒んで……いのちの君を殺してしまった」。キリストは「いのちの君」、救いの創始者です。また「聖なる」、内的に聖(きよ)い方であった。「正しい」とは、当時の律法、道徳に照らしてみて完全である、という意味です。内側にも外側にも立派なイエス。これを拒んだのは、宗教的な偏見や嫉妬(しっと)からでした。
「しかし、神はこのイエスを死人の中から、よみがえらせた。わたしたちは、その事の証人である。そして、イエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなたがたのいま見て知っているこの人を、強くしたのであり、イエスによる信仰が、彼をあなたがた一同の前で、このとおり完全にいやしたのである」
使徒行伝3章15~16節
あなたがたは殺したけれども、このイエス・キリストは蘇(よみがえ)って今も生きている。生きている証拠に、イエスの御名を呼びさえすれば、このキリストがやって来て、地上に肉体をもっておられた時と同様に、こういう現象が起きるのだ、とペテロは言うんです。
だから彼は、自分の力や信心深さで何かをしない。それをなさせるのはイエスの御名である。その御名を呼ぶとイエスの御霊、聖霊がやって来るからです。「イエスの”御名”」とは、その本質を表すんです。イエスは救い主・メシアである、神の霊が注がれた者である。こういう信仰がわき起こると、足なえのような者に急に力が入って立ち上がりました。

神は獣のような者にも
多くのクリスチャンは、キリストは自分たちだけの神だと思っております。キリストはクリスチャンにだけ顕現(あらわ)れると思っている。今の神学者や牧師さんたちは、宗教宗派にとらわれたような、制限された存在がキリストだと思うかもしれません。
だが、キリストはクリスチャンだけのものではありません。使徒行伝を読むとわかりますように、世から捨てられ、自分でも身をはかなむような乞食の男にも、御名を呼ぶ信仰、キリストにすがる信仰がわき起こりましたら、キリストの霊はやって来て、内側からその人を立ち上がらせてしまうほどの力が働いた。この力は今も働きつつあります。
先ほど、詩篇73篇が読まれました。その中にこうあります。
わたしは愚かで悟りがなく、あなたに対しては獣のようであった。
詩篇73篇22~23節
けれどもわたしは常にあなたと共にあり、あなたはわたしの右の手を保たれる。
詩人は、自分が悟りなく獣のようであった時にも共にありたもうたお方よ! と言っております。神が共にありながら、それに気がつかない。同様に、この乞食の男の目にも、キリストは覆い隠されていた。
だがペテロが、「金銀は私にはない。けれども私の持っているものをあなたに与える。ナザレのイエスの名によって立ちて歩め!」と言った時、乞食の心にむらむらとキリストにすがろうという心がわきました。この時、彼の心に信仰がわきました。わいた途端に、磁石が鉄を引きつけるように、キリストに吸い寄せられて立ち上がることができました。
私たちはキリストを、神の御霊をクリスチャンだけのもの、また信心深い人だけのもののように思っておりますけれども、詩篇73篇では詩人が、自分の心は真っ暗で、不信仰で、獣のようであった時にも、共にいたもうた神様! といって叫んでいます。
こういう神様でなかったら、私はとても救われませんでした。自分が立派だから救われたわけじゃありません。せっぱ詰まってすがるような気持ちでおった時に、キリストに吸い寄せられた魂でしかない自分。ほんとうに獣のようであった人間、こんな自分にも伴ってくださるのが神様である。
この考えをみんながもちましたら、人に対する考え方がもう少し違ってくると思うんです。よく、「あの人は駄目だ。この人は見込みがない」と言うことがありますけれども、神の目には一視同仁であって、神は獣のような者とも共に住みたもう。しかし、神と共にありながらそれを感じないとは、実に残念なことです。
私は、クリスチャン以外にもずいぶん、神の人を知っております。「ああ、この人は神の御霊が共にありたもうお方だ」と思うような人をたくさん知っております。その逆に、クリスチャンと称しながら、「この人は世の人よりもなんと愚かだろうか、汚ないだろうか、さもしいだろうか」と思う人があります。また、自分もそのようになる場合がある。
キリストはクリスチャンだけの独占物ではありません。このような乞食にも御業を働きたもうお方である、ということがわかりますと、ほんとうに皆さんの信仰が変わってくると思います。どんな人をも、信仰さえわき起これば救うことができるのが、いのちの君、キリストであります。そのことを、ここで強調しております。
神の子の姿に立ち帰る
ここまででしたら、単なる神癒(しんゆ)が行なわれたということにすぎませんが、ペテロにとってそれが目的ではありません。そのことをきっかけに、大事なことを申したいんです。
「さて、兄弟たちよ、あなたがたは知らずにあのような事をしたのであり、あなたがたの指導者たちとても同様であったことは、わたしにわかっている。神はあらゆる預言者の口をとおして、キリストの受難を予告しておられたが、それをこのように成就なさったのである。だから、自分の罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて本心に立ちかえリなさい。それは、主のみ前から慰めの時がきて、あなたがたのためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを、神がつかわして下さるためである」
使徒行伝3章17~20節
ペテロは、そこに居合わせた人々、師のイエスを十字架につけた者たちが驚いて見つめているのに対して、憤りをぶちまけるようなことはせず、「あなたがたは知らずにあのような事をした」と言って上手に心を和らげさせて伝道しております。そして、「自分の罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて本心に立ちかえりなさい」と言いました。
原文では、「悔い改める」は「μετανοεω メタノエオー」というギリシア語で、「回心する、心が引っ繰り返る」という意味です。「後悔する、懺悔(ざんげ)する」ではありません。仏教には、「廻心(えしん)」という言葉があります。それに近いでしょう。
また、「本心に立ちかえれ」の原文には「本心」という字はありません。このギリシア語「επιστρεφω エピストレフォー」は「向きを変える、引っ繰り返る、回転する、回帰する」という意味です。人間は本来、神の子ですから、獣のようでなく、神の子らしく神に立ち帰ることが大事です。立ち帰りさえすれば、自分の罪をぬぐい去っていただけます。
キリストは今も十字架に血を流しつつ、その血によって清められるように、と働いておられる。だれでも罪(宗教上の罪とは、人が神を信ぜられず神を拒むこと)がぬぐい去られることを願う。そのためには、まず悔い改める、回心することが大事です。回心した途端、十字架の上なる盗人にすら、「今日なんじは我と偕にパラダイスに在るべし」(ルカ福音書23章)とキリストが言いたもうたようなことが起こる。
私たちはお互い、獣のように神を知らぬ者であったけれども、ある時、翻然(ほんぜん)と回心するというか、廻心する気持ちが生じると、ぬぐわれたように自分の心が変わってまいります。どうしてこういう変化が起きるのだろうか?
蘇りの時と共にやって来るキリスト
「それは、主の”み前から慰めの時がきて”、あなたがたのためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを、神がつかわして下さるためである」(3章20節)。これが大事です。原文は「主のみ前から」ではなくて、「主の”み顔”から」です。神の光り輝く御顔から何が流れ出しているかというと、「慰めの時」が来るという。
「慰めの時」とは何か。ある英訳聖書は「times of revival タイムズ オブ リバイバル」と訳しております。リバイバル(蘇り)の時がやって来る。神の御座から私たちに流れ込んでくる、このリバイバルの時に乗って何が遣わされてくるかというと、キリスト・イエスがやって来られるというのです。またこの「慰め」とは、原文では「αναψυξεως アナプシュクセオース」で、「ανα アナ(再び)+ψυχη プシュケー(息、命)」 からできた語ですから、「慰め」というよりも「息づき、蘇り」と訳したほうがよい。英訳の「revival リバイバル」が、それに近いわけです。あるいは、「times of refreshing タイムズ オブ リフレッシング」という訳もあるように、「再び新鮮にする、活気づける時」であります。
主の御前から「息づきの時」がやって来る。十字架の暗い日々が続いたが、ペンテコステの日に天からにわかに堰(せき)を切って流れあふれるように「息づきの時」がやって来ました。その「時」の流れに乗ってイエス・キリストが来たりたもうた、とペテロは言うんです。こういうキリストの来たり方という福音は、他のキリスト教会では聞きません。初代教会の信仰と、説き方がだいぶ違うということにお気づきになりませんか。
預言者イザヤは言いました、「主は、せき止めた川を、そのいぶきで押し流すように、こられる」(イザヤ書59章)。主エホバの宗教が全く行き詰まってしまった時、主はそのようにして来られた。同様に、ペンテコステの日に、神の川が決河怒濤(けっかどとう)の勢いで流れてきました。その時、人々の胸に来たりたもうたのは、キリスト・イエスご自身の霊でした。
この霊を私たちが受け取る時に、あの生まれつき足が利かない男のように、運命に苦しむ者まで立ち上がって生き返るんです! これが原始福音の伝道であります。
どうか今日、主が、せき止めた川を押し流すように、神の霊を洪水のごとく皆の胸の中に流れ込ませ、キリストが私たち一人ひとりに臨在してくださるよう祈らざるをえません。
未来からやって来る時間
私たちの切に願うことは、主の御顔から発してくる息づきの時に触れることです。このタイムズ・オブ・リバイバル、蘇りの時、息づきの時が流れてくる、というのですから、信仰の「時」というものは、普通の人の考え方とは違います。
時は、過去から現在に、そして未来へというように流れてゆくものだと人々は考えております。「自分の過去が悪いから私の現在も悪い。どうせ、未来もつまらないだろう」と考えるのが、普通の人の時間観念でしょう。
ところが聖書の時間観念は、これとは別です。過去に引きずられてだんだん落ち目になってゆく人間に対して、未来から、主の御顔から息づきの時がやって来る。この時の流れに出合うと、すっかり魂の方向が変わってしまう。水の流れが変わると水車も回転が変わってしまうように、神に背を向けていた魂も主に向かって廻心してしまう。私たちはぜひとも、このような時の観念をもつことです。未来から流れてくる祝福の時間があるんです。
多くの人は、後ろを振り向いて暗い過去を見つめます。しかし、宗教的な時の考え方をもつようになったら、「過去はどうでもいい。神様! あなたが未来から、私の知らない未来から、滝のようにドーッと祝福の時を、リバイバルの時を流してください。そうすれば、私の運命は今までの流れから方向転換するでしょう」と言って祈れます。ここに普通の人の時間観念と、宗教的時間観念の違いがあります。
お互い、過去はどうでもいい、現在はどうでもいい。大事なことは、自分の未来を変えるような力に、そういう時間に触れることです。美しの門の前に座っていた乞食は、希望もなく、ただ朽ち果ててゆくだけでした。しかしペテロがキリストの御名を叫ぶと、息づきの時がやって来て、足なえの男を変化せしめました。こういう救いに私たちは与(あずか)りたい。
幕屋の聖会に行くと、こういう時間の流れにぶち当たりますから、皆の人が「どうしてこんなに息づき、うれしいのでしょう」と言われる。どうしてと言われても、この事実は説明できません。だが経験した者は、「ああ、ありがたい。もったいない」と言わざるをえない。信仰のシの字もなかったのに、どうして自分は信ずるんでしょう、と驚くほどです。
また、その息づきの時に触れたならば「あの人は不信仰だから、のたうち回って死ぬだろう」と思われていた人でも、立派に御名をたたえて死んでゆきなさる。十字架上の盗人がキリストに触れて回心したように、パラダイスに入る経験があります。
「悔い改めよ」とは、自分で後悔することではない。この”主の御前から来る時に触れる”だけで自然と悔い改める、翻然と神に立ち帰る。それをせよ、とペテロは言うのです。
多くの人がイエス・キリストを2000年前の歴史の中に探そうとする時に、聖書は何と語っているか。今も神の御前から、御顔の光から出る、時の流れに乗ってキリストは来たりたもうのである。「せき止めた川を押し流すように」聖霊はやって来る。その時、人々の運命が贖われ、変わるのである。まことに獣のようでしかなかった者にもこういう恩寵(おんちょう)の流れを、生命の川を注ぎたもう神様に、心から感謝いたします。
どうぞ、キリストが決河怒濤のように、霊の流れに乗って来たりたまわんことを、一人ひとりの胸に来たりたまわんことを祈ります。
(1970年)
本記事は、月刊誌『生命の光』872号 “Light of Life” に掲載されています。