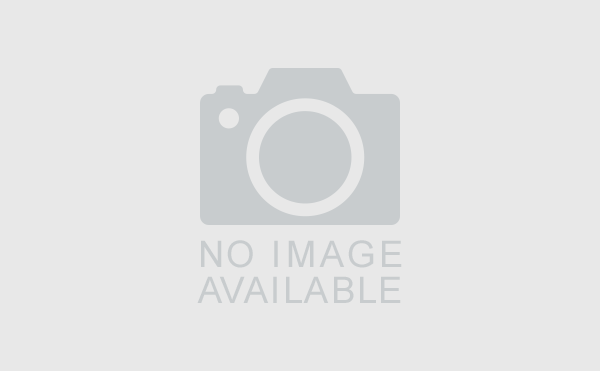聖書講話「神の臨在に帰れ」使徒行伝2章
現在、使徒行伝の講話を掲載しています。この書は何かの教えではなく、イエス・キリストが地上を去った後、弟子たちが聖霊を受け、神の力を現した行動の記録です。キリストの宗教において最も大事な「聖霊による回心」も、この使徒行伝にたびたび記されています。
今回は使徒行伝2章を通し、手島郁郎が赤裸々に真情を吐露しつつ語っています。
宗教というものが、何か儀式を守ったり、宗教哲学の研究をしたり、あるいは静かに瞑想したりすることのように思われるとき、キリストの福音はそういうものではありません。福音とは、天上にある神の国の生命が、聖なる御霊が地上の人間たちの上に降(くだ)り、そして人々が救われ、尊い神の生命に生かされはじめる、ということであります。
主イエスが地上を去られる時、都に留(とど)まって祈るようにと言われたので、120人の者が一心不乱に、心を一つにして祈った。すると、あたかも地上の陽電気と天上の陰電気が反応して雷となるように、聖なる御霊が彼らの祈っていた部屋を満たしました。そして皆に不思議な変化が、人間革命が起きました。これはただ一回限りのものではない、遠くに住む人たち、また子々孫々に与えられるべき贖いである、と聖書は記しています。
使徒行伝2章でペテロが、「悔い改めよ。罪の赦(ゆる)しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマ(注1)を受けよ」と申しております。ただ「罪が赦される」という消極的なことではなくて、積極的なこととして「聖霊の賜物を受けるであろう」と言いました。そして、「この曲がった時代から救われよ」と勧めると、3000人の人たちが、聖霊によるバプテスマを受けました。
ここに、今のキリスト教界の贖罪論という教理を信ずる信仰とは、原始福音が全然違っていたことを見ます。初代教会の人々が聖霊に感動して不思議な宗教経験に入ったように、私たちもせっかくキリスト教の信仰を志した以上、キリストが弟子たちに、また後代の者に至るまで念願したことを、自身に体験しなければなりません。宗教とは個人個人が体験し、また集団的にも体験すべきことであって、議論されるべきことではありません。
先日、ある大学の先生とお話ししましたが、今は神学校でさえ、左翼的な造反学生が煙草を吸いながら議論しているという。だが宗教は、まず自分が神を体験すべきことです。体験して、それを聖書で確かめ、さらに聖書を理想にして歩む。優れた聖者が歩いた道を模範にしてなお学ぼうとする者に、聖書の研究は大事なことです。ところが、神体験を抜きにして、「信仰とは何ぞや」という教理論、理屈から先に入ってゆくとき、理屈はわかっても、自分で体験したことのない者には、ほんとうにわかるものじゃありません。
近ごろは日本でも、パパイヤといった南方の果物が輸入されてだれでも食べられますが、昔は日本には出回っていませんでしたから、本物を食べるまでは何度説明してもわからない。
「台湾に行くと、パパイヤがうまくってね。かぼちゃのような外見で、匂(にお)いをかぐと母乳のような、チーズのような匂いもするし、味は甘いし、とにかくおいしい果物だ」と聞いても、チーズと母乳の匂い、かぼちゃとではつながらない(笑)。このように、先に説明を聞いて想像したものと、実際食べてみたものとではずいぶん違います。それと同じでして、宗教は体験すべきことなのです。せめて、体験した人に学ぶべきです。
ところが、神学校の先生のように体験したことのない人が、体験したことのない者にまず理屈から話してゆきますから、キリスト教とはこういうものなんだ! と思い込んだら、本物のパパイヤを持ってきたって、「これは違う! 私はこう思う」と言って話が通じません。そこが、原始福音と普通の教会などとの信仰の違いです。
(注1)バプテスマ
一般には、キリスト教の洗礼のこと。元は、ギリシア語で「浸すこと」の意。当時のユダヤ教で、体を清める時や、異教から改宗する時に行なった儀式に由来する。
宗教にとって何が大事なのか
「祈る」という一事を例に取ってみても、クリスチャンには「祈る」ということが何か、よくわかっていない人たちがいる。否、宗教というものがよくわからずに信仰している。
ですから、宗教は大切だと言うが、どうしてかを問うと、「人生の深い意味を悟るために宗教は大事だ」とか「宗教によって人格を高めるためだ」とか「宗教運動が起きないと、社会が改善されない。だから必要だ」などと、人はいろいろに言います。もちろんそれに反対ではありません。しかしながら宗教固有(プロパー)の問題として、宗教でなければ、否、どうしてもキリストの宗教でなければならない、本質的なものは何かを問うこと、それが先です。
イエス・キリストは、まず「祈りに祈れよ」と言われた。ほんとうに祈ることが大事です。深く祈って神と偕(とも)に生きておる人でしたら、どんなに無学な人でも不思議に神を知っているものです。しかし、それを抜きにして神学などを勉強した人たちは、全然神がわからない。わからないどころか、この病はますますひどくなります。
ですから、大事なことをほんとうに突き詰め深めてゆかねば、私たちはキリストが目的とされた不思議な宗教経験を、自分たちの上に成就できぬように思うのです。
キリスト教会に行きますと、「やあ、牧師さんのお説教、今日はよかった」などと言います。しかし使徒行伝2章では、ペンテコステの日にペテロがずっと話しておりますが、「その時、いい説教であった」とだれかが言ったなどとは書いてありません。人々はペテロの言葉を聞いて”強く心を刺され”、ペテロやほかの使徒たちに「兄弟たちよ、私たちは、どうしたらよいのでしょうか」と言ったので、ペテロが、聖霊にバプテスマされよ、キリストのバプテスマを受けよ、と答えたという(2章37~38節)。
人々が聞きつつ、「自分が間違っていた!」と言って、心を刺されるような集会だったことを書いています。これは道徳的な裁きではないですよ。そのショックにあてられて、3000人の人が神に立ち帰った。こういう伝道が行なわれたというのです。
私は自分で聖書を読みながら、果たして今のような集会を続けていていいのかしら、と思うことがあります。聖書を重んじ、聖書講義をする――これは無教会主義の伝統ですけれども、しかし大事なことは、ほんとうに祈ることです。聖書を講義しても、もう祈らずにはたまらない感情がわき起こるのでないならば、駄目ですね。

切実なる真の祈り
無教会というグループでは、聖書は研究します。けれども、祈禱会ということはほとんどしません。一人静かに黙想することを祈りと思っている。幕屋のように雄たけびして祈るのは、うそじゃないかと批判するんです。
だが、明治時代に祈りをもって多くの身寄りのない孤児たちを養育した石井十次(注2)先生は、雄たけびして祈った人でした。当時を知る人の話では、孤児院に近づくと、遠くからでも、「ああ、十次先生、祈ってるな」と聞こえた。そのくらい大声で率直に「神様、こうしてください、ああしてください」と祈った人でした。自分の家族を養うだけでも大変ですのに、多くの孤児たちを養ったのです。危急存亡の時には、恥も外聞も忘れて、もうじっとしておられませんよ。「神様、助けて!」と言わなければたまらない。
私の長男がまだ乳児のころ、疫病にかかって死にそうになったことがあります。父親というものは、赤ん坊に対して母親ほどの愛情はないものです。しかし、目を白黒させて、コーヒー状のものをゲッと吐きましたら、もうおしまいです。これが最後かと思いましたら、急に私に愛情がわいてたまらぬようになった。医者は匙(さじ)を投げて、来てもくれない。病院であろうが、看護婦が変な顔をしようが、わが子ですもの、「神様!」と叫んで私は狂うように祈った。そうしたら、生き返ってしまった。私は、神がこのように鮮やかに祈りにこたえたもうお方であることを知らなかった。それまでも、いやしの体験は何度かありましたが、そんなに真剣に祈ったことはありませんでした。これは私の若き日の経験です。
祈りということを、人は何と考えているでしょうか。静かに瞑想することを祈りと考えている人があります。また、聖公会やカトリックでは祈禱文があって、それに節をつけて朗誦(ろうしょう)することを祈禱だと思っています。
また、いろんな人が手紙の中に「どうぞ、お幸せになるように祈ります」と書きますが、それは「希望します」という程度のことでして、私においてはそんな程度じゃないんです。「是が非でもこれを実現してくださらなければ、神様、困ります。何か打つべき手を私に打たせてください」といったことを、私は神と問答しているわけです。
ここに、「祈る」といっても、またキリストの宗教といっても、人それぞれに違いがあります。しかし聖霊が降って、前に会ったこの人と、今日のこの人がこんなにも違うだろうか、と思うほどの変化を来たす力――これがペンテコステの宗教経験でした。それをくぐって、「人新たに生まれずば、神の国を見ることあたわず」のキリストの言葉のとおり、上より新たに生まれるという経験があるんです。ぜひともこれを物にしたい。
(注2)石井十次(1865~1914年)
明治期を代表する慈善事業家、キリスト者。当初、医師を目指していたが、23歳にして医学生を辞め、孤児たちの救済に専念する。岡山孤児院を創設し、多くの孤児たちを育てた。
宗教の目的とは何か
いつぞや、大阪の天王寺公園を朝早く散歩している時でした。あそこは乞食がたくさん集まる所です。ふと、この人は乞食だろうかと思うような人が、朝早くから太陽に向かって拍手(かしわで)を打って祈っているんです。いつまでもいつまでも、東の方を向いて合掌しています。その乞食のじいさん、復員軍人か何かでしょうね、よぼよぼの姿でした。
私がじっと電柱のわきから見ていますと、10分も20分も合掌したまま、じっと立っています。それだけでない、だんだんと顔が変わってゆくんです。何を拝んでいるか知りませんよ。しかし満足そうな顔になってゆく。私はこの乞食の老人のほうが、その付近で朝から晩まで金もうけの話に夢中になっている人たちよりも、よっぽど神に近いと思いました。
私はその時、ほんとうに恥じました。世界で最高の宗教といわれる聖書を信じている人間でありながら、自分は劣っていると思った。ただ独り乞食をしているところを見ると、恐らく罪を犯して転落してさまよっているのか。または戦争で生き残って帰郷してみると、妻子と死に別れて、わびしく暮らしつつ冥福を祈っているのか、それは知りません。しかし、その乞食のもつ神々しい霊的雰囲気、これは説明外でした。
宗教とは、英語で「religion レリジョン」といいます。これは、「結合、つながること」という意味のラテン語「religio レリギオ」から来ています。
私たち人間は神の子であり、神の国に生きる祝福された存在でしたのに、今や楽園(パラダイス)を失ってさまよっております。もう一度、神の国に受け入れられ、神につながる。もう一度、本来の自分を回復するところに、宗教の目的があります。偽りの自分、表面的な自分でない、真心の自分というか、神に、神の国に連なっている生涯、これを経験するところに、レリジョンという英語の意味があるのです。それを、ただ「宗教」と訳すと、キリストの「教え」と誤解されます。宗教は、神につながることです。神的な存在と合一することです。
私たちが宗教を志しているというときに、祈るということは何でしょうか。”神につながっている自分を発見すること”だと思います。ヘブル人への手紙11章に、「神に来る者は、神のいますことと、ご自身を求める者に報いて下さることとを、必ず信じるはずだからである」とあります。「神に来る」とは、神につながるために近づくということです。なぜなら、近づいてゆく者が神ご自身を求めさえすれば、神は豊かに報いたもうからです。神は決して祈りを聞き流したりなさらない! 必ず聞いてくださる!
数日前から私は、ある人のことを「どうしているかな」と心に思っておりましたら、その人がこの集会に来ているじゃないですか。「ああ、神様! あなたを求め、あなたに近づく人のことを祈っていると、あなたは聞き逃さずに、私が手紙を書くよりも早く、ここに連れてきておられます」と、私は涙に濡れました。神は生きておられる!
祈りとはこういうことです。単に神を瞑想せよ、などと聖書に書いてありません。祈りとは、神の存在するところに近づくことです。
詩篇16篇に、「わたしは常に主をわたしの前に置く。主がわたしの右にいますゆえ、わたしは動かされることはない」とあります。このように、今まで「神はどこにいるだろうか?」と思っていたのに、「見よ、今ここに!」といって神を経験する。これがペンテコステの経験、聖霊が注がれる経験なんです。これを受けない限り、どうしても直に神が感ぜられない。魂は神を慕うものです。しかしいくら教会に行っても魂が潤されず、ついにその求めを断念してしまう。そこには、ありありとした神の臨在を感じないからです。
青木澄十郎先生の回想
昨夜、祈っていますと、示されたことがあります。私が「だれさんの信仰が未熟だ。長年、信仰しながらどうしてわからんのだろうか」と言って、愚痴をこぼしたりすることがある。けれども、なに、私が悪いんです! 私が神の国から抜け出てきたようにして、ありありと神を示すことができぬから、神は遠くにおられるように皆さんが思われるんです。
いつか、京都の下鴨(しもがも)という所に、もう亡くなられましたが当時91歳の老牧師、青木澄十郎(注3)先生をお訪ねしたことがあります。日本は宣教100年といいますが、青木先生は生涯、日本のキリスト教の歴史と共に歩いたお方ですから、わけても尊敬しておりました。
いろいろお聞きしておきたいことがありましたが、まず、「先生の長い信仰生涯の中で、どなたにいちばん心打たれ、この人こそは神の人だとお思いでしたか?」とお尋ねすると、「松江で伝道しておられたバックストン(注4)先生に、明治二十何年ごろかにお会いしたが、この人こそは神の人だった」と言われる。そして、忘れがたい印象を物語られるのでした。
「私がお訪ねすると、先生が庭の生け垣から出ていらっしゃる。生け垣には、つる薔薇(ばら)がアーチのように咲いていたが、そのアーチの門に札が掛かっていた、“We now live in Eternity”(ウィー ナウ リヴ イン エターニティ 我らは今、永遠の中に生きている)と。先生はそこから天国の香りをつけて、私の前に現れた。何とも言えぬ輝きを顔に浮かべておられた。私は神が在(いま)したもうことを知った。いやあ、あの方はほんとうに神の人だった。あの人だけだった」と言われた。
(注3)青木澄十郎(ちょうじゅうろう)(1870~1964年)
日本の牧師。プリンストン神学校に留学。帰国後、同志社神学校などで教鞭を執った後に、神戸日本基督教会の牧師となる。旧約聖書、新約聖書についての著述を多く残し、聖書本来の福音に帰ることを提唱した。
(注4)B・F・バックストン(1860~1946年)
明治期に日本で活動したイギリスの宣教師。聖霊によるバプテスマを強調。日本伝道隊を設立、松江を中心に多くの弟子を育てた。弟子たちの群れは「松江バンド」と呼ばれ、日本の福音派キリスト教の源流の一つとなる。
神に連なる生涯に
使徒行伝は、イエスの弟子たちの間に起こった聖霊の降臨の出来事を書いております。ペンテコステについては、それが起きるような祈りが人々の間にあったということです。天に対して地がこたえる態度であった。こういう祈りが今、忘れ去られております。もう祈らずにはおれないような不思議な雰囲気をわかせることが、本当の信仰の姿だと思います。
宗教とは、福音というキリストの宗教は、神につながる、連なることです。神に連なるとは、”祈りにおいて連なる”ことです。ですから、祈り心でいることが伝道者にとってはいちばん大事です。バックストンについて青木先生が言われたように、ほんとうに永遠の国から今、抜け出てきたように永遠を生きていること、これが私たちの模範であると思います。
けれども、私は自分がそうでないために多くの人を導けない。いろいろな方の感話をお聞きしていて、祈りということをこうも誤解しておられるかと思うと、私が悪いと思う。あれを思い、これを思いと、人のことで思い煩って、神ご自身と私は歩いていない。
そう思うと、主様、とても今日は集会ができません。私はこの程度の信仰経験ではたまりません。人様を欺く。こういうことはすべきでない。青木先生がバックストンに感じたような姿こそ、私の模範でなければならぬ。人が何と言い、かにと言おうが、人はどうでもよい。神だけにつながって、神とだけ結びついている状況、これが宗教の極意です。
神様、どうかこの僕(しもべ)を変えてください!(泣きつつ) 聖書講義をするというならば、人を意識したのでは駄目です。常に神に連なって生きて、それを皆さんが感ぜられるような状況でないならばいけない。宗教は理屈でないから。ほんとうに自分を恥じております。
聖書の説明や講義は、空(むな)しいように思う、もし神と一つになって生きる喜びを失ったら。もちろん、私は失ってはいません。失っていないからいいけれども、青木先生が「90年の生涯、たった一人、神の人を見た。そして自分は襟(えり)を正して神を信ずるということを始めた」と言われたほどのものが我らの信仰にならない限り、私は駄目だと思うんです!
ペテロが語ると、「人々は心を刺され」とありますが、これはだれの罪、彼の罪、あの罪と責め立てることではないのです。ペテロがいるだけで、人々は皆、魂に渇きを覚えて、「聖霊にバプテスマされたい!」という願いを激しくもつようになった、というのです。
ペテロは、そのように不思議な臨在感をもっておりました。キリストは、ほんとうに栄光の主である、天にも地にも栄光の主であることを、ペテロを通して現されました。地上におられた時も不思議なご存在だったキリスト。今、天上にあっても昔同様に信ずる者を通して、奇(くす)しき御救いを、贖いを、生命の注ぎをなしたもうのがキリストです。
今日は感情が高ぶって、順序を追ってお話ができません。どうかお許しください。今までここに立って、口幅ったい聖書講義をしたものだと、私は悔いておるんです。私たちに大事なことは、神に連なる生涯、神と偕なる生涯、明けても暮れても贖い主キリストと偕にある生涯、どうかこういう祝福された経験を、みんなで回復しとうございます。
ペテロが祈り祈った末に、立ち上がり、輝いた顔を示した時に、人々は心刺されて皆が神に立ち帰ったという。今までが、過去が何であれ、皆が神に立ち帰るようにあらねばならない。これは人間の話ではできません。美しい説教ではない、よいお話ではない、聖霊が働くから心刺されるんです。キリストご自身が前に立ちたもうからです。どうぞ、みんなで祈ってください! 大声で祈ってください!
(1970年)
本記事は、月刊誌『生命の光』870号 “Light of Life” に掲載されています。