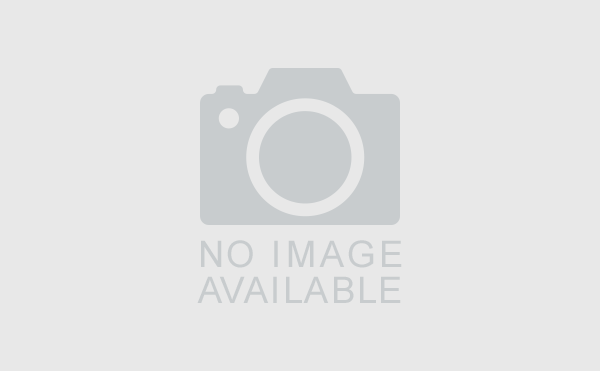聖書講話「真の福音を嗣ぐ者は誰か」使徒行伝2章5~18節
イエス・キリストが世を去られた後、それまで信仰の弱かった弟子たちは神の霊を注がれ、力強い信仰者へと変えられました。しかし同時に、その出来事に対してさまざまな批判をする人たちも出てきました。現代でもペンテコステ同様の状況が起こる時、批判的な人たちが現れます。そのような声に対して、弟子のペテロは何と語ったか。
今回も使徒行伝第2章から学んでまいります。(編集部)
「ペンテコステの日にキリストの教会は誕生した」と、聖アウグスチヌス(注1)は言いました。
イエス・キリストは十字架につけられ非業の死を遂げられたが、復活され、弟子たちに「父なる神の約束を待て」と言い遺して天に帰られた。その御言葉のとおりに聖霊降臨(ペンテコステ)の出来事が起きた時に、今まで逃げ腰で弱かった無学なペテロが、上よりの力を受けて、エルサレム――イエス・キリストを殺した、最も恐ろしい宗教の町――の真ん中に立ち、宗教家たちの見ている前で、人々に向かって堂々と聖書を引いて演説しました。
弟子たちは無学な貧しい人々ばかりでしたのに、この力が臨むと、素晴らしい宗教活動を展開してゆき、キリスト教はやがてローマ帝国を打ち変えて、全世界に広まる宗教とはなったのです。これはだれもが認めるところであります。
もしペンテコステにおける出来事がなかったならば、とてもキリストの宗教は成立しませんでした。本一冊お書きにならなかった、ナザレの田舎大工の子・イエスの説いた宗教などというものは、とても残るはずがありません。しかし、なぜこれが、ものすごい宗教エネルギーを利かせて広まっていったのか! ここに、ペンテコステの出来事を深く、何度も私たちが学ばねばならぬ理由があります。
しかし、ただ研究をするのではないのです。大事なのは、もう一度私たちは、キリスト教を創り出したエネルギーの源に触れたい、ということです。
前回読んだ使徒行伝2章には、「五旬節(注2)の日がきて、みんなの者が一緒に集まっていると、突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起ってきて、一同がすわっていた家いっぱいに響きわたった。また、舌のようなものが、炎のように分れて現れ、ひとりびとりの上にとどまった。すると、一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉(原文は「異種の言葉、異言(いげん)」)で語り出した」(1~4節)とあります。
その時に、皆が「聖霊に満たされた」ということが大事です。聖霊に満たされると、不思議な状況になって、「御霊が宣(の)べしむるままに、異言を語りだした」と書いてあります。この聖霊降臨の出来事が起きますと、人々はどのように反応したのでしょうか。
(注1)アウグスチヌス(354~430年)
古代ローマ帝国において、キリスト教が公認された時代、北アフリカを中心に活躍した教父。若い頃は異教を信奉し、放蕩な生活を送ったが、母モニカと聖アンブロシウスの影響により回心。後に、キリスト教の正統思想の確立に大きな貢献をする。
(注2)五旬節
ギリシア語で「第50」を意味する「ペンテコステ」の訳語で、ユダヤ教三大祭りの一つ「七週の祭」のこと。過越の祭から50日目に当たり、春から初夏のころに祝われる。キリスト教では、使徒行伝のペンテコステが聖霊降臨の時とされる。
人々の驚き
さて、エルサレムには、天下のあらゆる国々から、信仰深いユダヤ人たちがきて住んでいたが、この物音に大ぜいの人が集まってきて、彼らの生れ故郷の国語で、使徒たちが話しているのを、だれもかれも聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんで言った、「見よ、いま話しているこの人たちは、皆ガリラヤ人ではないか。それだのに、わたしたちがそれぞれ、生れ故郷の国語を彼らから聞かされるとは、いったい、どうしたことか。……あの人々がわたしたちの国語で、神の大きな働きを述べるのを聞くとは、どうしたことか」。みんなの者は驚き惑って、互いに言い合った、「これは、いったい、どういうわけなのだろう」。しかし、ほかの人たちはあざ笑って、「あの人たちは新しい酒で酔っているのだ」と言った。
使徒行伝2章5~13節
人々は「これは、いったい、どういうわけなのだろう」(12節)と互いに言い合った。原文は「τι θελει τουτο ειναι ティ セレイ トゥート エイナイ」となっていて、「これは、何であることを欲するか」というのが直訳です。すなわち、これは一体どう思ったらよいのだろうか、どう解釈したらよいのだろうか、という意味ですね。
このようにペンテコステ的状況が発生する時に、信仰のない部外者は驚き惑い、慌てふためくということが起きる。もし起きないならば、ペンテコステ的状況ではないのです。
集まってきた群衆のうちで、信仰のある人々は皆、「一体どうなんだろうか」と言い合ったが、11節に「神の大いなる御業(みわざ)を語るのを聞く」とあるくらいですから、言外に、「自分もそうありたい。けれども、どうなんだろうか」という意味を含んでおります。
同様に、我々原始福音の群れに起きているペンテコステ的現象は、神の大いなる御業です。人間の業ではない。なぜ異言を語るという宗教現象が起きるのか? ある事典では、「リバイバル(信仰復興)に伴う付随現象である」と書かれています。それで、リバイバルを待望する祈禱会を行なう教会もあります。しかし、起きないのです。人間が願ったからといって、どうにもならないあるもの、これがペンテコステである。突如として人間の世界に神が臨ましめる、神の大いなる業だからです。
もしこのペンテコステの状況が起きなかったならば、とても私たちの原始福音運動は成立しなかったでしょう。私をはじめ皆、無学な者たちの一群です。しかし、神はこういう者たちをとらえて、ご自分の働きを進めてゆかれます。だから御名をほめたたえるのです。
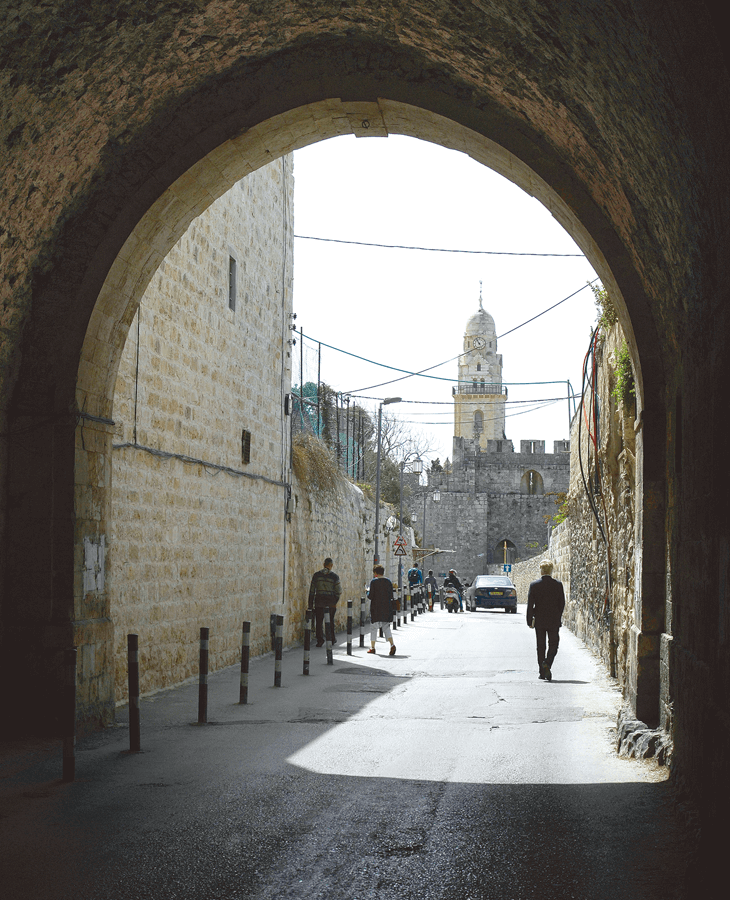
旧約聖書以来の預言の成就
しかし、わけのわからない人は、「あの人たちは新しい酒で酔っているのだ」(13節)と言って嘲笑(あざわら)いました。ここの「新しい酒」と訳されている原語「γλευκος グレウコス」は、できたてのまだ発酵状態にあるぶどう酒のことをいいます。それは穏やかな酒ではなく、きつく甘いぶどう酒ですね。聖霊に満たされて異言状況にある人々に対して、「ああ、甘いぶどう酒を飲んだんじゃないか」と嘲(あざけ)っているのですから、どういう悪評をしたかがわかります。
それに対して、イエス・キリストの筆頭の弟子であったペテロが、他の11人の者と共に立ち上がって、弁明して語っております。
そこで、ペテロが11人の者と共に立ちあがり、声をあげて人々に語りかけた。
使徒行伝2章14~18節
「ユダヤの人たち、ならびにエルサレムに住むすべてのかたがた、どうか、この事を知っていただきたい。わたしの言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから、この人たちは、あなたがたが思っているように、酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨエルが預言していたことに外ならないのである。すなわち、
『神がこう仰せになる。
終りの時には、わたしの霊をすべての人に注ごう。
そして、あなたがたのむすこ娘は預言をし、
若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。
その時には、わたしの男女の僕(しもべ)たちにも
わたしの霊を注ごう。そして彼らも預言をするであろう』」
聖霊に満たされることが大事
ペテロが今までの逃げ腰ではなく堂々と語った記録を、こうやって聖書には書いてあります。「酒に酔っていると言うが、誤解もはなはだしい。この出来事は、預言者ヨエルの預言の成就である。末の日に神の霊が肉なるものに注がれる時に、すべて預言者となる。預言状態になるのだ」と、弟子たちが異言で神を賛美している状況について弁明している。
すなわち、異言といい、預言といい、皆一つのことです。異言状態とは、預言状態の、ある状況をいうのです。これは、旧約聖書の時代以来そうです。
後にイスラエルの最初の王となるサウルが、預言者サムエルによって油を注がれた時に、「あなたは預言者の一群に出会うであろう。その時、主の霊があなたの上にも激しく降(くだ)って、あなたは彼らと一緒に預言をし、変わって新しい人となる」と言われた。そして高き所から下ってくる預言者の一群に出会った途端にサウルに神の霊が激しく降り、預言状態になった、とあります(サムエル記上10章)。
預言状態というのは神の言葉を何か語るのですから、異言と同様に、自分の意識的な言葉を語るのではありません。ある意味の無我の状態です。頭だけで表面的に生きている者が急にある刺激を受けると、腹のどん底からわき上がってくる状況のことです。
それで、ペンテコステの出来事が起きました時に、ペテロをはじめ120人の一群に、今まで経験しなかったような霊的経験がわき起こってきた。これをわき起こらせたものは、天よりの響きであり、天よりの力であります。聖なる御霊の働きであります。聖なる霊が私たちに働きかけてくる時に、私たちは思わぬ状況に入ります。
大切なことは、異言を語り、預言状態になることよりも、まず”聖霊に満たされる”ことです。それに伴って、私たちの状態が変わってくるのだ、預言状態になるのだ、ということをよく知らなければなりません。聖霊に満たされる時に、私たちは不思議に新しい人と変わる。変わったことの一つの”しるし”として、異言を伴う状況がまず現れる。
異言は、コリント人への第一の手紙12章にも書いてあるように、最も初歩的な賜物であります。とにかく、切に御霊の注ぎを求めることが大切です。
神の霊が人間に臨むと
先日、アメリカに行きましたら、ある方が言われます、「先生のお子さんを見てみると、みんな立派です。先の奥さんが亡くなられているのに、どうやってそんなに育つんですか」 と。立派というのは、信仰をもっているという意味ですよ。一般に、アメリカの日系人の家庭では、若い者が祖父母の信仰を嗣(つ)ごうとしてくれない、という。ですから、かの地の老人方の質問は、「どうして子供たちが信仰を嗣いでいるのか」ということです。
私の答えはこうです、「それは”聖霊によるコンバージョン”(回心)です。これがある時に、一つ御霊に皆が統一される、一つになることができます」と。
私の前の家内が亡くなる少し前でした。私たち幕屋の一群に、ペンテコステさながらのリバイバル状況が起きました。長男は中学生でしたが、阿蘇での集会(1950年11月)に、大人に交じって出ておりました。そこで、急に歓喜が突き上げてきたという。それからというもの、歌わずにおられなくなった。それまで音痴というか、全然歌わなかった彼が歌いだしたので、音楽の先生が驚いて、「どうしてそんな素晴らしい声をもっているのか。とにかく、君は音楽部員になれ」というわけで、その年の12月から合唱団の一人に加えられました。その学校は、全国の合唱コンクールにおいて1位を取るような名門校でした。何が彼をそう変えたか! 本人も知っているとおり、あの時、阿蘇において集った者60人の上にひとしくペンテコステの霊が注がれた時に、彼は変わったんです!
またある画家の方も、私たちの集会に出て聖霊によるコンバージョンをされてからは、霊感的に絵をかかれるようになりました。まあ、その方は芸術の手段として求めなさった。しかし、私たちにおいては手段ではない。信仰の生命なのであって、これが目的です。後のことは、付随的に与えられるんですね。
神の霊が私たち人間に、生まれながらの肉なるものに宿るということの不思議さ! その顕(あらわ)れは一人ひとり違いますが、そのころは皆がそれを証ししたものです。「こんな不思議なことがありました」と喜び合いました。
「聖霊がなんじらに臨む時に、力を受ける。そしてキリストの証人となる」と書いてあることは、ただ教理の問題ではないんです。”実験すべきこと”なんです。この力に与(あずか)ると、どんなに祝されることか! 御霊の約束に与ることが、私たちの福音であります。この宗教を福音――よきおとずれ――とは、よくぞ言ったものです。
異言は聖霊の賜物
使徒行伝を見ても、ペンテコステ的状況に接して、聖霊のバプテスマを嘲る者、また、「この現象は一体、何だろうか」と言って批評する者、中には「神様が大いなる御業をなしたもうた」と言ってあがめはするが、自分はどうもなろうとしない者たちがいます。しかしもう一つは、ほんとうに弱く卑しめられた者たちがこの御霊に与って祝された。
こういう4種類の人たちを、この聖書の短い箇所に見ますが、この中でだれがキリストのエクレシア(注3)の形成者であったでしょうか。そしてだれも今、このペンテコステの経験をしようとしない。もしそれをしようとする者がいると、嘲る。そして、その嘲る者たちが、自分はクリスチャンだと称するから困るんです。これは、どこに原因があるのか。
14節を見ると、ペテロが声を上げて人々に語りかけました。「ユダヤの人たち、ならびにエルサレムに住むすべての方々、どうか、このことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けてほしい。あなたがたが思っていることとは違う」と弁明しています。
私自身、異言について説いて、インテリ・クリスチャンからずいぶん批判、攻撃されましたから、現代でもペンテコステ的経験をもつ者に対して、多くの牧師やクリスチャンがどのように思っているか、よく知っています。
彼らは「聖霊に満たされることはいいにしても、満たされて異言状態になるのはどうもおかしいじゃないか。子供は教えてもらうから言語を語る。それなのに教わらずに言語を語るのはおかしい。それは病的だ」と言う。異言という言葉が、彼らに全く不可解なんです。それで「異国(ことくに)の言葉、他国の言葉で語りだした」と訳しています(2章4節)。しかし、これは「異なる言葉、異質の言葉」という意味です。
使徒行伝10章の終わりにも、ペンテコステと同様の状況が書かれております。
「ペテロについてきた人たちは、異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれたのを見て、驚いた。それは、彼らが異言を語って神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペテロが言い出した、『この人たちがわたしたちと同じように聖霊を受けたからには、彼らに水でバプテスマを授けるのを、だれがこばみ得ようか』。こう言って、ペテロはその人々に命じて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた」(45~48節)
ここでもわかりますように、ペテロは「我々にかつて聖霊が臨んだ時のように、この人たちは聖霊を受けた」と言い、伴(とも)の者たちは「聖霊の賜物が注がれたのを見て」驚きました。ここで言われる「聖霊の賜物」とは何か? 異言を語るのを聞いた、とあるとおり、”異言”です。「他国の言葉」ではありません。ペテロたちは、自分たちがかつて経験した、聖霊降臨の時のような異言があったればこそ、「聖霊が注がれた」と言いえたのです。
また一方で、ペンテコステ派といって異言を強調する人々もいるけれども、深いところまで究めて教える人がおらず、ごまかしの異言を語っている。偽のペンテコステ派、異言派というものがのさばるために、皆が「あれが異言派なら、警戒したほうがいいですよ」と言って信じないのです。
(注3)エクレシア
キリストの弟子たち、クリスチャンの集団のこと。聖書では、「キリストの体」とも表現される。現代では「教会」と訳されるが、本来はユダヤ教の「会衆 カハル」のギリシア語訳で、場所や建物を指すものではない。
真のエクレシアを復活させるため
このように、聖書の信仰においていちばん大事なことが受け入れられないために、皆がほんとうに損をしております。キリスト教は2000年間、取り巻きのワイワイ言う人たち、嘲る人たち、これは一体何だろうと疑う人たちばかりに受け継がれてきて、肝心なペテロその他120人の系統は全く消えてしまっている。時々起きても、皆潰(つぶ)されてしまう。
私が今しきりに考えていることは、「神様、あなたはこうやって私たちのグループを起こし、満たしておられますが、どうしたらこれが日本民族に長続きするのでしょうか」ということです。それも、「組織や教派によらず、どうしたらキリストの説かれた原始福音が伝わってゆくでしょうか」との問いです。
これは結局、”本物の人”が出る以外にない。原始福音は、本物のクリスチャンによって受け嗣がれてゆくからです。教派によっては受け嗣がれない。一人ひとりが神によって生まれなければ、どうにもならない。そのためにどうしたらよいか。神様、どうしたら、このペンテコステを聖別することができますでしょうか。いかにして一般の教派と区別して、原始福音を聖別することができるかが、後代に対する私たちの責任だと思います。
使徒行伝2章でペテロが言うように、「終わりの日に神の霊がすべての人に注がれる。その時、私たちの息子や娘は預言をし、若人は幻を見、老人は夢を見るであろう。男女の奴隷たちも聖霊を注がれて預言をする」。これが初代教会の性格でした。
聖霊が注がれると、預言的、異言的な性格を常にもつ。しかしそれを失う時に、既成教会や教派のようになってダイナミックな信仰がすっかり形骸化(けいがいか)し、静的な宗教に変わって落ち着いてしまう。だから、私たちの原始福音運動はどこまでも教派の形をとらない。いつも生き生きとした、御霊に満たされた人が続々と現れて、革新、革新していったらいいのです。信仰が古いとか、学歴があるとか、優れた閲歴があるとかは二の次、三の次です。大事なことは、いつも新しい霊に満たされた器が続々と出現して、御霊を絶やさず、消さずに進めてゆくことだと思います。
人が何と言って批判してもよい。神様が私たちを通してなそうとしておられることは、ご自分の身体なるエクレシアを、もう一度、復活させるための御業だと思います。聖霊に満たされる時に、不思議な状況に変化します。どうぞ、もういっぺん、決定的な変化を遂げとうございます。
(1970年)
本記事は、月刊誌『生命の光』866号 “Light of Life” に掲載されています。