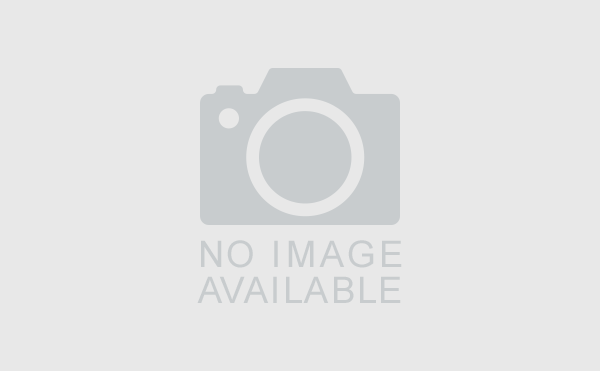随想「瑞穂の国の宝なる糧 ー祈りの民の米食文化を想うー」

『生命の光』誌編集員 河盛尚哉
今年は米価高騰に始まり、米不足、米の買い占め、政府の備蓄米の大量放出などなど、「令和の米騒動」と騒がれるほど、米にまつわる問題で日本列島が揺れた1年でした。
祈りと信仰の米作り
私は、幕屋の信仰をもって農作業に励んでおられる、ある米作農家のご主人を訪ねたことがあります。現在81歳になられますが、「あと5年は米作りに力を入れたい」と言われる情熱には、心を打たれました。
「米作りのお仕事の中で、いちばん大切にしていることは何ですか?」と尋ねると、「夜明けと共に目覚め、稲田の畔道(あぜみち)を、天と対話するように祈りながら歩く、その祈りから1日を始めることです」と答えられました。いつも祈りを第一にして米作りに励んでおられる姿に、深い感動を覚えました。
私はかつてその方から、収穫されたばかりの新米を幾度も頂いたことがあります。その味は、群を抜いて美味(おい)しく、心の中から幸福感が込み上げたことを思い出しました。
久しぶりにその方とお話しして、あの新米の美味しさと幸福感の秘密がわかったような気がしました。
最も重要な「新嘗祭」の日
11月のカレンダーを見ると、23日は「勤労感謝の日」という休日になっていますが、先の大戦で敗戦するまでは「新嘗祭(にいなめさい)」の日でした。
「新嘗祭」とはその年の新米の収穫を祝い、翌年の豊穣を祈願する、古くからの祭儀です。皇居における天皇の大祭をはじめ、全国の神社ではもちろんのこと、各家庭でも祝われた日でした。
ところが、敗戦を喫するや、日本の崇高な心が受け継がれていくことを危惧する占領軍の強い影響下に、「新嘗祭」は宗教性を遠ざけた「勤労感謝の日」という、日本語としても全く意味不明の休日に変わってしまったのです。
しかし、「新嘗祭」はカレンダーから消えた現在でも全国の神社で続けられ、ご皇室では粛々と執り行なわれています。宮中で執り行なわれ、天皇がお出ましになる30を超える祭祀(さいし)の中でも、「新嘗祭」は最も古く、かつ重要な祭祀です。
11月23日、天皇は皇居内の神嘉殿(しんかでん)において、天神地祇(てんじんちぎ)にその年に収穫された新米をお供えになり、国家の繁栄と国民の幸福を祈られます。その後、天皇親(みずか)らもカミガミに供えられた新米を召し上がられるのです。この祭儀が深夜にわたって2度行なわれます。
その新米の源泉を求めて流れを遡(さかのぼ)ると、以下に述べるように、高天原(たかまがはら)の稲田にまでたどり着きます。
このように、神霊が臨在するという極めて宗教的な状況下で、1つの釜(かま)で炊き上げられたその聖なる新米を天皇も天神地祇と共にお召し上がりになることにより、天皇に宿る霊的な力が新たにされるといわれます。
稲穂を携えての天孫降臨
「新嘗祭」は、神話の時代にも行なわれていました。有名な天照大御神(あまてらすおおみかみ)の「天の岩戸隠れ」の物語の始まりを、『古事記』は次のように記しています。
「速須佐之男命(はやすさのおのみこと)は……勝ちに乗じて天照大御神の作られる田の畔を壊し、その溝を埋め、また天照大御神が大嘗(おおにえ)をなさる御殿に糞(くそ)をしてまき散らした」
(現代語訳)
この記述で注目すべきは、高天原には、天照大御神おん自らが作られる稲田があったことと、その稲田から穫(と)れた新米で「大嘗」すなわち「新嘗祭」がなされていたことです。
高天原の主宰神でありながら、天照大御神はさらに上位の天つカミガミに高天原で穫れた新米を献(ささ)げて、「新嘗祭」を執り行なわれていたのでした。
そして、天孫の邇邇藝命(ににぎのみこと)が降臨されるに際しては、三種の神器と共に高天原で穫れた神聖な稲穂を持って、高千穂の峰に降り立たれました。その後、悠久の歳月を経て、日本で米作りが始まったと伝えられています。
内なるものを新たに
米は1年の節目に、正月はお餅(もち)、ひな祭りはひなあられ、端午の節句はかしわ餅やちまきなど、さまざまな食物に姿を変え、いろいろな花を咲かせて、私たちの生活や人生を祝福してくれます。歴史を通じて、米はいかに私たちの生活や文化を豊かに支えてきたことでしょう。
世界の各国、各民族にそれぞれ、欠くことのできない主食があります。米はもちろん、麦類や、トウモロコシ、イモ類や豆類などが挙げられるでしょう。それらの収穫を感謝し、豊穣を祈願する祭りもまた、世界各地で行なわれてきましたが、その多くは世俗化して、宗教的な意味合いを失いつつあるようです。
その中で、「新嘗祭」の最大の特徴は、神霊の臨在下で神人共食が行なわれるという宗教性にあるのだと思います。天皇が天神地祇と食を共にされ、また天照大御神もさらに上位の神霊と共に新嘗をなされるという、神聖な祭祀が私たちの米食文化の根底を支えていることに、思いを致します。
米とは、そうした深い宗教的意味合いをもつ食物であって、日本人は古来、米には霊的な力が宿ると信じてきました。
以前は宮中や神社だけでなく、全国の村々町々で、また各家庭で行なわれていた「新嘗祭」。その意味を深く想う時、日本民族の中には単に食糧に感謝するだけでなく、1年のこの時、人間の内なるもの、霊魂が強められることを大事にする心があるのだと知ります。
私はキリスト者として、このような精神を尊びつつ聖書を読みます。
イエス・キリストは「天から下ってきたパンを食べる人は、決して死ぬことはない。わたしは天から下ってきた生きたパンである」と、ご自身の中にたぎっていた神の生命を受けて生きよ、と言われました。
11月23日の「新嘗祭」の日には、米作農家の方々のご苦労を思いつつ新米の豊かな収穫を祝い、私たち国民の幸福を祈られる天皇陛下に感謝を捧(ささ)げたい。
そして、わが国が未来永劫(えいごう)にわたって、稲穂が日の光に黄金色に照り輝く「瑞穂(みずほ)の国」でありつづけることを祈りたいと思います。
本記事は、月刊誌『生命の光』872号 “Light of Life” に掲載されています。