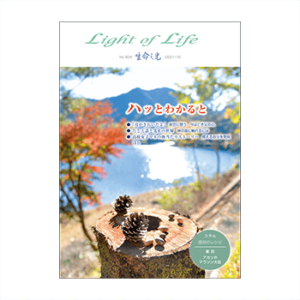随想「死ぬるに時あり」
『生命の光』誌編集人 藤井資啓
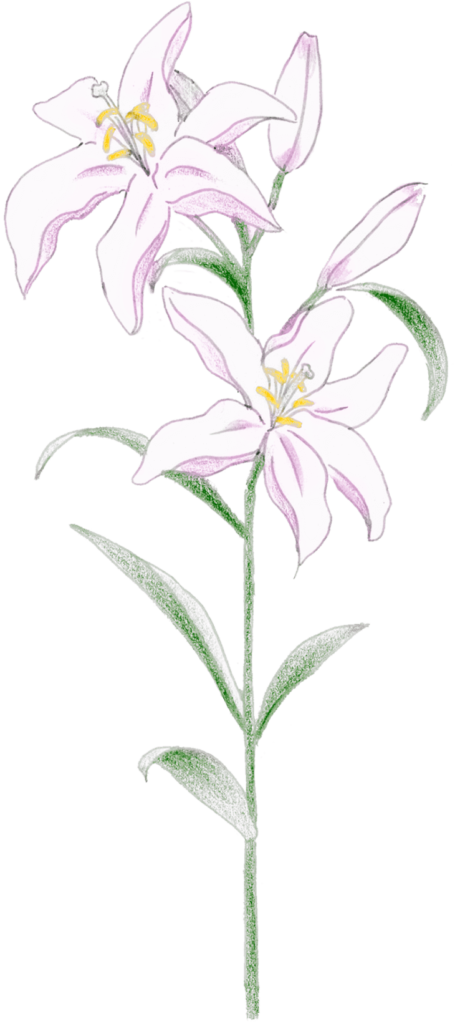
ある方のお見舞いで、地方都市の大きな病院を訪れた時のことです。その方がおられた大部屋の人々は、ほとんどがご高齢の老人たちで、だれもがたくさんの管を体に取り付けて、ベッドに横たわっておられました。その情景に、私は大きなショックを受けました。
そのような姿で「生きる」ことを、本人たちは望んでおられるのだろうか。人間の最期の時を尊厳をもって迎えるには、私にはあまりにも痛々しい姿に思えたのです。もちろん個々のご家族の事情と、その方を思う心情あってのことで、他人の私が、十把一絡(じっぱひとから)げで物を言うつもりはありません。
ただ、現代の病院での医療では、口から食事を摂れなくなった人に、胃瘻(いろう)などで栄養を補給しながら肉体を維持しつづける。それがほんとうに当人の心情と事情を深く理解したうえでのことなのか、と思ったのです。
平穏な最期を迎える
「病院での死は、敗北です。病院は『治す』ことを目的にした施設です。……近代医学というのは、死を排除しようとする闘いのなかで進歩を遂げてきたのです」と、ある医師が語っておられます。(『こうして死ねたら悔いはない』石飛幸三著)
しかし、この医師は、人間というものは、死に向かって自然と自分の体の中で準備をしているものであり、薬や医療の力で肉体を元気づけようとはせず、平穏のうちに死に向かわせてあげることのほうが本来の望ましい姿であると思う、と訴えておられます。
「老い」の先にある「死」は、だれもが必ず迎える時です。その死をどのように迎えるのか。
私の母は3年前に亡くなりましたが、何年も前から兄と私に、「私が病に倒れても、絶対に延命治療をすることのないように願う」との手紙を送ってきていました。母は熱心なクリスチャンでしたから、死んだら天国に行くことをひたすら祈り、夢みていたことでしょう。
それで母の病状が悪化して入院した時、病院に最低限の手当てにとどめてもらうようお願いしました。担当医からは、「最期は多少苦しまれることもあるでしょうが、それも短時間ですから」と言われました。
そのとおり、最期は少しの間、苦しい息遣いのようすでしたが、やがて呼吸は穏やかになり、静かに安らかに天に召されてゆきました。
次なるステージへ
私は、人の「死」とは神様が用意された人生の次なるステージへの移行だ、と思っています。
母が亡くなって1年ほど後、私に初孫が生まれました。その時、私はとても不思議な感動と喜びを覚えました。
天(あめ)が下のすべての事には期(とき)があり、すべてのわざには時がある。生まるるに時があり、死ぬるに時がある。
伝道の書3章1~2節 私訳
と聖書にあります。
人が死んで地上から姿を消す。それは悲しみを伴うかもしれませんが、天が下に生まれた人間である以上、必ずその時は訪れるのです。神様は私たち一人ひとりに、死を通し、天における次なる段階を用意しておられるのだと思います。
しかし一方では、また新たな生命が地上に生み出されてくる。そこには大きな喜びと希望が与えられます。人の死も誕生も、すべては神様の御手の中にある厳粛なことなのです。
人の一生は、人間の思いでは計り知ることのできない、はるかに大きな天のご計画の中にあるのではないでしょうか。そして神様の御思いは、次の世代へ、次の世代へと継がれてゆく。
私たち人間は、そのような大きな時の流れの中で、神様に生かされている存在なのです。

本記事は、月刊誌『生命の光』823号 “Light of Life” に掲載されています。