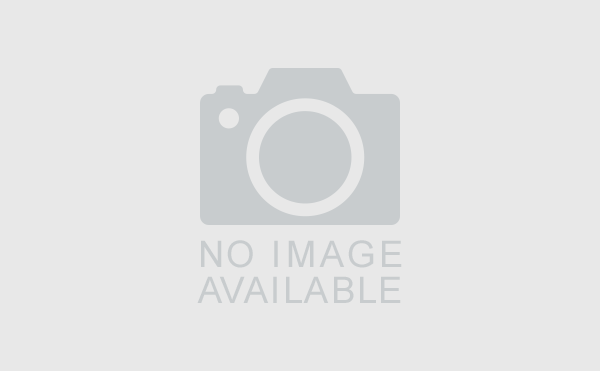エッセイ「慰めを奏でる音色」
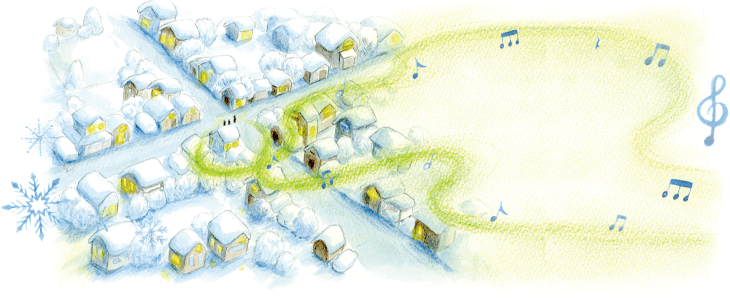
伴 千津子
大正生まれの父は、どこか「ハイカラ」な人でした。
貧しかった学生時代に、友人たちとハーモニカ・バンドを組み、得意げにタンゴを奏でていたそうです。
大東亜戦争中、インドネシアで従軍していた時でも、父はハーモニカを手離しませんでした。夜ごと吹いていると、その音色に心打たれた上官から、「おれのために吹いてくれ」と頼まれたこともあったとか。おかげで上官にとてもかわいがられた、と話していました。
ですが、日本の敗戦は父を絶望のふちへと追いやりました。祖国のためにすべてをかけて戦った熱血漢の父だったからこそ、敗戦とともにその価値観は崩れ、挫折感(ざせつかん)と喪失感で苦しみました。
冬の恒例行事
復員した父が奉公先として向かったのは、能登半島の輪島にあった親戚宅でした。
ある日の掃除中、ふと一冊の本が父の目に留まりました。それが”聖書”だったのです。そこにつづられているひと言ひと言が、父の胸を打ちました。
「この中には、命をかけても惜しくないものがある」と思うまでに。
教会に通うようになった父が、1人で聖書を開いて祈っていた時のこと。急に体が震えるほどの畏(おそ)れを感じ、地面にひれ伏してしまったのです。それは、父が初めて神様に出会った瞬間であり、生涯忘れることのできない回心の体験でした。
そんな父には、クリスマスになると決まって行なうことがありました。それは、クリスマスの賛美歌を歌いながら町を歩く、「キャロリング」。私たち姉妹や教会学校の子供たちにとっては、冬の大切な恒例行事でした。
父を先頭に、子供たちが輪島の町をぐるりと歩き回るひととき。中でも、朝市通りを端から端まで、力強く響く父のハーモニカに合わせて歌いながら歩いた時の光景は、今も鮮明に覚えています。
救い主イエス・キリストのご降誕の喜びを伝えたい。その願いが、父のハーモニカの音色には込められていました。
その音色を聞きながら、大好きな町を歩いたキャロリングは、父との大切な思い出で、私にとって故郷・輪島の原風景です。
人格が一変するまでに
神様に触れ、回心したことを喜んでいた父でしたが、教義や教理を大事にする教会の在り方には疑問を感じていました。二十数年続いた教会生活は、「キリストの福音はこんなはずじゃない」と思いながらの、苦しい祈りの日々だったそうです。
そんな時、一冊の『生命の光』をきっかけに、幕屋の聖会に参加しました。
その時の体験を、父はよく話していました。
「うれしくてうれしくて、信仰するとはこんなに素晴らしいことなのか、神様がこんな身近に私を愛してくださっているということを、理屈なしに教えられた」
その聖会を境に、父は人格が一変してしまったのです。そして、私の頭に手を按(お)いて祈ってくれた時、私にもありありと聖霊が臨み、回心してしまいました。
やがて父は、実家で家庭集会を始めました。そして、能登半島に天の祝福が及ぶことを願いながら歩みつづけました。その姿は、父が亡くなった後もハーモニカの音色と共に能登の友人たちの心に深く残っていた、と聞いた時は、胸が熱くなりました。
よみがえってくる父の姿

昨年の元日、能登半島地震が起こり、父と過ごした実家は全壊しました。
かつてハーモニカを吹く父と一緒に歩いた、輪島の朝市通りも焼失し、思い出の地は一瞬にして姿を消してしまいました。
けれども、震災以前に遺品として保管していた父のハーモニカは、私の手元に残りました。それを眺めていると、能登を愛し、キリストの福音を伝えることに命をかけ、天の祝福を届ける思いで吹いていた父の姿がよみがえってきます。
今年のクリスマスの日、父の小さなハーモニカを握りしめながら、私も祈りをささげます、「どうか、今も悲しみと痛みの中にある被災地を、天からの慰めと祝福の音色で包んでください」と。
本記事は、月刊誌『生命の光』873号 “Light of Life” に掲載されています。