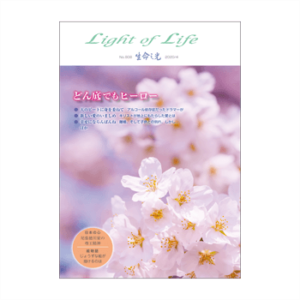聖書講話「新しい愛のいましめ」ヨハネ福音書13章34~35節
皆さんは、キリスト教には厳しい掟(おきて)やいましめがあると思われるかもしれません。でも、新約聖書でイエス・キリストが残された「いましめ」は、ただ1つでした。それは十字架にかかる前、弟子たちに語られた、「互いに愛し合いなさい」ということです。
普通、世の中でも「人を愛さなければいけない」といいます。キリストが示された愛は、そのような道徳的な愛と何が違うのでしょうか。(編集部)
「わたしは、新しいいましめをあなたがたに与える、互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによって、あなたがたがわたしの弟子であることを、すべての者が認めるであろう」
ヨハネ福音書13章34~35節
イエス・キリストは十字架にかかる前夜、弟子たちに「わたしは、新しいいましめをあなたがたに与える」と言って、初めて「いましめ」というものをお与えになりました。
多くのクリスチャンは、人が救われるのは信仰によるのであって、「いましめ」はいらないのではないか、と思いやすい。宗教改革者のマルチン・ルター(注1)は、「行ないによらず、ただ信仰によって救われる」ということを強調しました。だが、ただ「信仰があればいい」ということになると、人間は自分の平生の生活を省みなくなります。
私たちの信仰は、一歩一歩、どこまでも前進しなければだめです。もうこの辺でいい、ということはありません。このことを欠いては、信仰がほんとうに生きてきません。
ここで、十二弟子の一人のユダがイエスを裏切る決心をして、食事の席から出ていった。人間、普通の時はいましめはいりません。けれども、人生の難関や試みに直面して、信仰をもってどのように突破しようかと思い悩むときに、いましめが信仰を生かしてくれる。ここに、イエスが弟子たちにいましめをお与えになる必要があったのです。
(注1)マルチン・ルター(1483~1546年)
ドイツの神学者。カトリックからプロテスタントが分かれた宗教改革の中心的人物。「人は善行ではなく、信仰によって義とされる」と主張。聖書に根拠をもたない教会制度や儀式の廃止を訴えた。
イエスの言われた愛とは
ここでイエスの与えられたいましめは、「互いに愛し合え」ということですから、ごく易しいことのようです。しかし、真に「愛する」というのは、非常に難しいことです。
仏教では、「慈悲」という言葉は使いますが、「愛」という言葉は嫌います。「ただ憎愛なければ、洞然(とうねん)として明白なり」という有名な禅の言葉があります。信心する上でいちばんいけないのは「憎愛」だというのです。これはむしろ、執着という意味でしょう。
たとえば、男女が恋愛関係にある場合は、お互いに愛し合っています。ところが、どちらかが裏切って他の男や他の女に心を向けたりすると、それまで燃えていた愛情が憎しみに変わる。今のほとんどの文芸作品に書かれている愛情は、このような男女間のトラブルです。世にいう愛というものは難しいもので、昨日まであんなに愛し合っていたのに、今度は殺してやりたいと思うくらいの憎しみに変わる。こういう愛憎は退けなければいけないといって、仏教では執着や欲を断つことに主眼が置かれます。
もちろん聖書が説いている愛は、そんな憎しみに変わるような愛ではありません。けれども、「愛する」とは、ある人の感情が特別な者たちに向けられることをいうのならば、イエス・キリストが弟子たちを愛されたことも同じです。
ヨハネ福音書13章の最初に、「イエスは、この世を去って父のみもとに行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して、彼らを極みまで愛したもうた」とあります。これは、ご自分の愛情が特別な者に注がれるという濃ゆい愛であって、「人類を愛せよ」などという道徳的な薄い愛ではありません。
旧約聖書のレビ記には、「あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない」(19章18節)という言葉があります。これはユダヤ人の特徴をよく表しています。ユダヤ人は、この人を愛そうと思ったら、自分を愛するようにとことん愛してくれます。先年、イスラエルに行った時も、多くの人がこちらが困るくらいにお世話してくださいました。どこかへ一緒に行くと、たとえ貧乏であっても、金をはたいて尽くしてくれます。東洋では、「君子の交わりは、淡きこと水のごとし」といって、淡泊な愛を理想としますから、ユダヤ人のような激しく濃厚な愛は、私には時としてたまらないこともあるほどです。
だが一方、東洋的な儒教道徳では、自分を抑えれば愛が行なえる、と考えますから、愛するといっても極めて倫理的です。たとえば、本当はあの人にお金をあげたくない。でも、あげねばならない。それで、自分を抑えてお金をあげる。けれども、本心からでないものを「愛さねばならないから」というのでくれても、あまりうれしくはないですよ。義理で愛されるということほど、嫌なものはありません。本心からの愛は内なる発露であって、自分の内側からわき出てくる愛でないならば、本当の愛ではありません。

もし「愛をもつ」ならば
さて、「新しいいましめ」というときの「新しい」は「καινος カイノス」というギリシア語です。新約聖書では「新しい」という言葉について、「νεος ネオス」と「καινος カイノス」という2つの語が使われています。「νεος ネオス」が時間的な新しさをいうのに対して、「καινος カイノス」は質的な新しさをいいます。ですから、「新しいいましめ」とイエス・キリストが言われるときに、今まであったものとは全然質の違ういましめ、という意味です。
キリストが地上にもたらされた愛というものは、全く新しい愛というか、弟子たちの想像も及ばない愛でした。それは、弟子たちが見てきたとおりです。最後の晩餐(ばんさん)の席では、キリストは弟子たちがご自分を裏切り、自分を捨てて去ってゆくことを知っておりながら、一人ひとりの足を洗われました。その夜、裏切り者になるユダに対しても食物を浸して渡し、「おまえを愛しているよ」ということを示して、最後の最後まで愛し抜かれました。裏切られることも許す愛とは一体、何だろうか。「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」(ヨハネ福音書13章34節)と言われるときの愛は、それまで弟子たちが知っていた愛とは全然違うものだった、ということがよくわかります。
果たして人にそれができるのでしょうか。しかし、愛は倫理ではありません。ここに「互いに愛し合うならば」とあるが、直訳すると「お互いの間で愛をもつならば」です。お互いの間に、キリストがもっておられた天的な愛があるならば、キリストの弟子である、というのです。これは「愛する」という動詞としての愛ではありません。「愛」という実体を表す名詞としての愛です。真にキリストの弟子であるならば、キリストがもちたもうた霊的な生命、愛という生命をもっているかどうかが一番の証拠となるのです。
初代教会時代に書かれたものに、クリスチャンを評して言った、「彼らはお互いに知り合う以前から愛し合っている」という言葉がありますが、そのことを端的に表しています。お互いが出会ってから愛するというならわかります。しかし、出会う前から愛し合っているという。あの人に会ってみたら好きになった、というような愛ではないのです。
「私が愛する」といって、自分中心の人が愛してくれても煩わしくなります。また、道徳的な「愛さなければいけない」という愛ではたまらない。しかし、キリストを信じる私たちに聖霊と共に流れ込んでくる愛、この兄弟愛というものは格別なものです。
愛は自ずからわいてくるもの
よく「自分の隣人がわかったら私は愛する」と言ったり、「私は伝道をしようと思うが、隣人はだれでしょうか」と隣人をどこかに求める人がいます。ところが、聖書の言う「隣人」とは「最も近しい人」という意味です。それは肉親とか、向こう三軒両隣に住んでいる人、という意味ではありません。心の距離がいちばん近い、親しい人という意味です。
ルカ福音書10章を読むと、イエスがある律法学者から「何をしたら永遠の生命を受けられますか」と聞かれると、「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。また、自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ」と言われた。すると、その律法学者は「では、私の隣人とはだれでしょうか」とさらに聞きました。だれが隣人かがわかりさえすれば愛することができる、というわけです。
それでイエスは、「よきサマリヤ人」の譬(たと)えを話されました。エルサレムからエリコに下る急な坂道で、強盗に傷つけられた旅人が倒れていた。エルサレムから下ってきた祭司や、信心深いはずのレビ人が通ったけれど、見て見ぬふりをして行った。しかし、ユダヤ人から嫌われているサマリヤ人の一人がそこを通りかかった時に、もう捨ておけずに近寄って介抱してやり、宿屋に連れていって面倒をみてやりました。イエスは、「その旅人にとってだれが隣人であったか」と問われました。愛された者にはだれが隣人かがわかるのです。この旅人にとっては、ユダヤ人たちから嫌われたサマリヤ人こそが隣人でした。
シナの孔子(注2)は、「仁(じん)を為(な)すは己(おのれ)に由(よ)る、而(しか)して人に由らんや」と言っています。ここでいう「仁」とは人を愛することですから、愛とは自分が愛するのであって、相手の人によるのではない、というのです。愛というものは自分からわき出てくるものであって、対象を見て愛するならば、それは客観化された愛であって、本当の愛ではありません。愛とは惻隠(そくいん)の情であって、込み上げてたまらぬような気持ちで愛するときに真実の愛なのです。
思い上がった気持ちで「私は隣人愛を実践します」などと言うなら、鼻持ちならないですね。「おれはあの人を愛したのに、あれはいっこうに感謝せん」などと言って、愛が怒りや憎しみに変わる。本当の愛はそうではない。全然報われるかどうかわからない。しかし、堪らずに愛した場合に本当の愛なのです。
母親が赤ん坊に乳を飲ませる時、母親は乳を与えるということが喜びだし、また赤ん坊は乳を飲むことが喜びです。そこに損得の関係はない。また母親に、自分が愛しているなどといった気持ちはない。もう、愛さなければ自分がたまらないのです。それに似て、本当の愛は対象によりません。ここに、聖書が言う愛の特性があります。
(注2)孔子(こうし)
紀元前6世紀に活躍した古代中国の思想家、教育者。堯(ぎょう)、舜(しゅん)、周公旦(しゅうこうたん)など聖人たちの政治を理想とし、戦乱の世において、徳を重んじ、礼をもって世を治めることを説いた。人間らしい愛を意味する「仁」を最高の徳とし、多くの弟子たちを育てた。
アガぺーとエロース
キリストが「お互いの間で愛をもつならば」と言われるときの「愛」は、「αγαπη アガペー」というギリシア語です。愛というとき、ギリシア語には「ερως エロース」という語もあります。
古代ギリシアのプラトン(注3)による哲学の根本は、エロースという思想です。今、「エロ的」などといって卑しめますが、元来悪い言葉ではありません。エロースというのは「あこがれの愛」、自分に欠けたものを補いたいという、価値のあるものを求める愛です。これはある意味で非常に大事なことです。真善美(しんぜんび)にあこがれるというときに、それは「エロース」です。古代のギリシア人が学問を愛するという精神も、このエロースから来ています。
一方、キリストの語られた「アガペー」は、より高いものを求めるのではなく、「下る愛」といわれます。神様が罪深い人間の苦しみを労(いたわ)り、愛されるというときに、高い者が下る、憐れむ愛です。価値があろうとなかろうと愛する、これがアガペーの愛です。
ここに愛といっても、「エロース」と「アガペー」という違いがあるのです。このことをニグレンというスウェーデンの神学者も言っております。自分より素晴らしいものを愛すること、これはだれでもします。けれども、それは愛する対象によって、愛が激しくもなり、衰えもします。それに対してアガペーの愛というのは、対象によらない愛です。
Tさんのお子さんには小児麻痺(まひ)という障害がある。しかし、その子を労り、愛している姿を見ると、母親は尊いと思います。愛すべき対象がどんな状況でも、母性愛の本質として愛せずにはおられないのです。このような愛がアガペーの愛に近いのです。
アガペーの愛は、相手に価値があって慕わしいから愛するのではない。慕わしかろうが慕わしくなかろうが、相手の状況に関係なくわいてたまらない愛をいうのです。これは、私たちキリストの御霊を受けた者が少なからず知っている愛です。また、お互いがもっているものです。これがいちばん尊いのです。
(注3)プラトン
紀元前5~前4世紀のギリシアの哲学者。ソクラテスの弟子で、対話による物事の探求を書に著し、西洋哲学の基礎を築いた。世の中の事物は、天上の理想の姿の反映であるという「イデア論」を説く。
試練を越えしめる愛
イエス・キリストが十字架にかかられるなら、弟子たちにも迫害が及ぶでしょう。そのような時、キリストは「互いに愛し合え」とお命じになった。「この愛をお互い燃やしさえするならば、どんなときにも信仰で生き抜くことができる」とおっしゃったのです。
10年ほど前、東京である誤解から、幕屋の人たちが世の中からひどい非難を受けるようなことが起きました。けれども、そのような試練の中、信仰を捨てるどころか、迫害がひどくなればなるほど皆が一つになって祈り、愛し合いましたから、天国のようでした。
私たちは信仰が冷えかかっているときに、お互い愛し合うことによって信仰が保てます。ただ一人で神を信じたら救われるというのでは、とても信仰は保てません。私たちはこうして熱く愛し合っているから、悪しき時代にあっても信仰で生き抜けるのです。
すなわち、試練を乗り越えるのにいちばん必要なものは愛です。私たちが、十字架のような迫害、恐ろしい試みの中を通るとき、愛だけが信仰を支えます。信仰が風前の灯(ともしび)のように消えそうになるときに、信仰の火を消さずに燃え立たしめるのは、キリストの霊を受けたお互いの間にあふれてくる愛、聖霊の愛です。
迫害の激しかった初代教会の時代、お互いが知り合う前から激しく愛し合っていたといわれますが、私たちもそれと同じような光景を少しでも現代の日本において見られるとは、なんとうれしいことでしょうか。
(1964年)
本記事は、月刊誌『生命の光』2020年4月号 “Light of Life” に掲載されています。